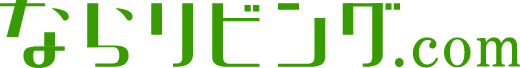豊原山長久寺(山添村) 八十八カ所石仏めぐり

奈良市市街地から車でおよそ1時間。奈良県の北東端に位置する山添村は、奈良県東部山間地域に広がる大和高原の一角にあたる。
村内にある東豊ベースHBcafeの取材に訪れたところ、そこで出会った村の観光ボランティアガイドの奥谷和夫さんから「おもしろい顔のお地蔵さんがいっぱい見られるよ」と聞き、立ち寄ってみることにした。
カフェから車で5分とかからず、毛原地区に到着。ここは、国指定史跡「毛原廃寺跡」がある地域。奈良時代の大寺院跡で礎石が当時のまま残っていることで知られる。目的の「おもしろい顔のお地蔵さん」は、長久寺にあると聞いたので、向かってみた。
道沿いの駐車場に車を止め、急な坂道を上る。強い日差しを受けて、心が折れそうになりながらもなんとか本堂に到着。案内板によると、この寺の創建年代は不明だが、古くから毛原区の住民の菩提寺として大切にされてきたそうだ。手入れの行き届いた美しい境内がそれを物語っている。

手入れの行き届いた本堂
おもしろい顔のお地蔵さんは、寺の奥にある四国八十八ケ所をイメージした霊場「大師山」にあるという。
この大師山は、明治7年に住職に就任した知龍上人が、仏法の興隆を願い、明治15年に信者や石工らの協力を得て、自然の山の姿を生かしつつ多くの石仏を安置して開いたと伝わる。
 どこまで続くのかと思うほど急な坂道
どこまで続くのかと思うほど急な坂道
急な山道を上ると、すぐに石仏に出会うことができた。最初は思ったほど「おもしろい顔」と思わなかったが、山道を進んでいくと、奥谷さんの言葉が理解できた。首の長い石仏やどことなく猿に似た石仏、今にも笑い声が聞こえてきそうなほど笑顔の石仏など、さまざまな石仏が、道沿いに安置されている。
「次はどんな顔だろう」と思うと、ついつい進んでしまう。親族や知人、自分自身に似ている石仏を見つける人もいるそうだ。




石仏の大きさはいろいろで、重機のない時代にどのように坂道を運んだのか。自分の損得ではなく、仏教の興隆を願うという崇高な目的のために、上人はこの山道を何度往復したことだろう。
上人の素晴らしい功績に思いをはせながら、「今日はここまでにしようと」下山を決意。
全てを回ると1時間は必要なること、さらにマムシが出没するとのことが理由。今回は入口付近だけにとどめておいたが、気温が落ち着く季節には、ぜひすべての石仏の顔を拝見してみたい。
吹き出す汗をぬぐいながら、山道を降り、マムシに遭遇しなかったことに安堵して、改めて看板を眺めて気づいた。どうやら逆回りしていたらしい。思い付きで訪れたことを反省した。
 境内にある大きなクスノキ
境内にある大きなクスノキ
最後に、カフェの店長から「驚きの蛇口があるから」と聞いていたので、探してみると、驚きの意味がすぐにわかった。蛇口の開閉に使うハンドルが通常の倍以上の水道を見つけた。なぜこんなに大きいのか…理由は不明だが、同寺を訪れた際は、こちらもぜひ見てほしい。(千)


写真左は通常サイズ。写真右がビッグサイズ
豊原山長久寺
山添村毛原
※このページの内容は2024年9月6日現在のものです。