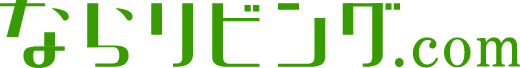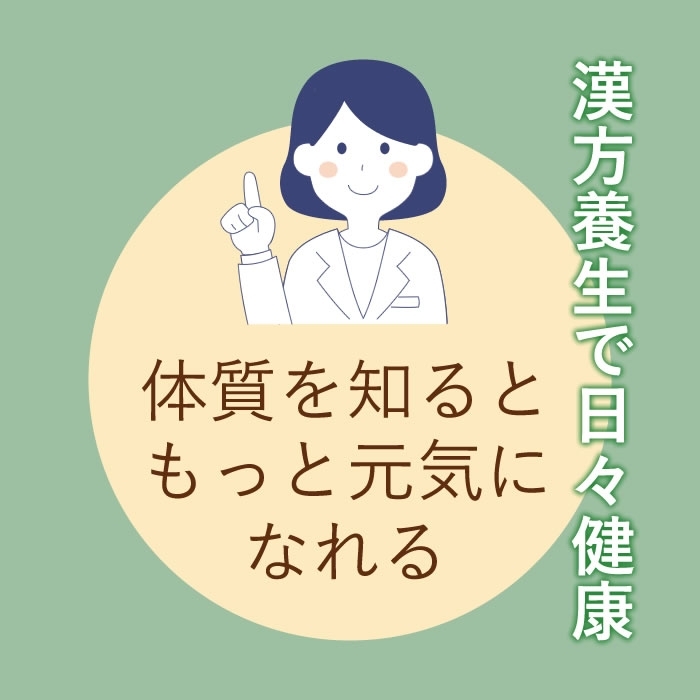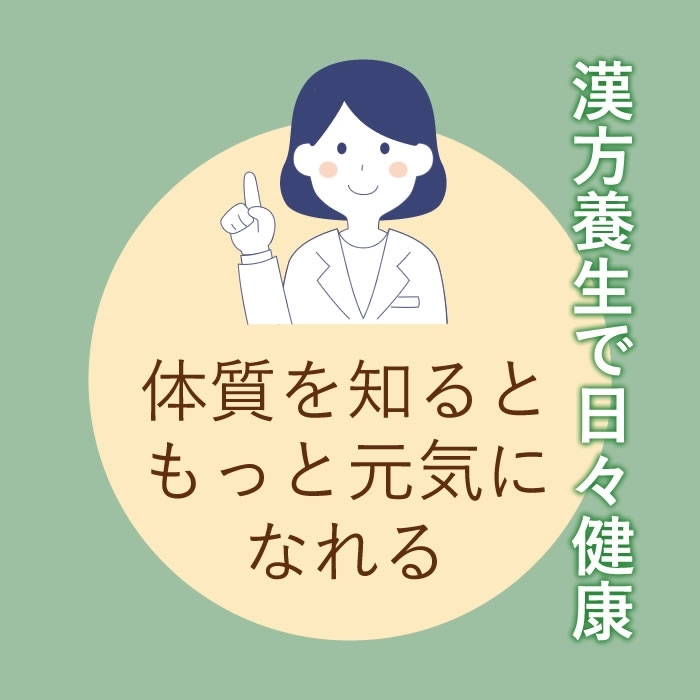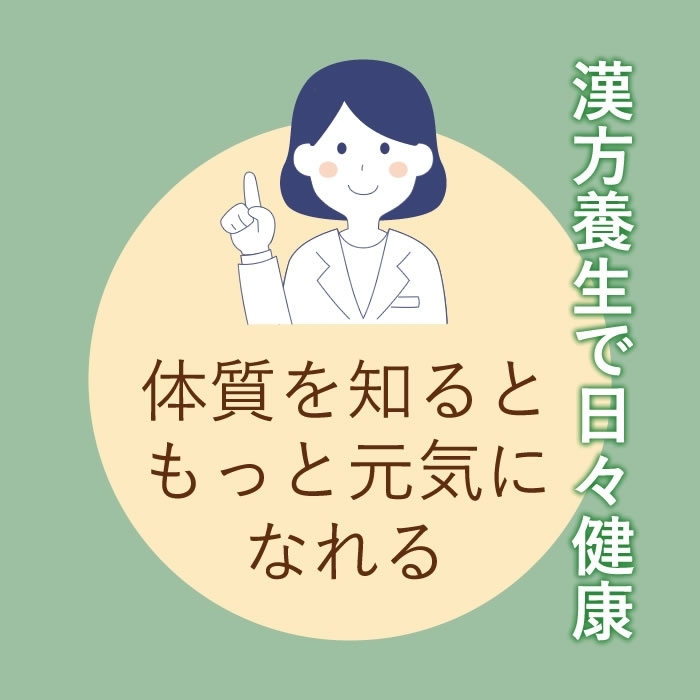漢方養生で日々健康~体質を知るともっと元気になれる~vol.46 「慢性疲労」にお悩みの方へ
漢方理論をもとに女性の悩みに応えてきた一陽館薬局のかしたに陽子さんに、健康を保つ秘訣を聞く連載企画。今回は、日常生活にも著しい支障をきたす疾患とされる「慢性疲労」についてのお話です。

「慢性疲労症候群」とは?
「寝ても翌朝に疲れを持ち越す」「休日にゆっくりしても体が重い」など、ご自身の体調との付き合い方にお悩みの人もおられるのではないでしょうか。
日常の疲れは休めば回復するものですが、近年は"ただの疲れ"ではなく「慢性疲労症候群」といった病気も注目されています。
「慢性疲労症候群」は、十分な休息をとっても回復しない強い全身倦怠感が、少なくとも6か月以上続き、日常生活に著しい支障をきたす疾患とされます。突如として発症する複雑な神経免疫系の不調により思考力・集中力の低下、筋肉痛、頭痛、睡眠障害、微熱、リンパ節の腫れなど、多彩な症状を伴い、原因不明のまま症状が長期化することが特徴です。
「自律神経」と「免疫」との関わり
ここでは病気になる前にできることを考えてみたいと思います。
私たちの体は、本来「エネルギーをつくる仕組み」と「エネルギーを回復させる仕組み」がバランスを取りながら働いています。ところが、ストレスや睡眠不足、栄養の偏りなどが重なると、この仕組みがうまく回らなくなります。
特に近年注目されているのが「自律神経」と「免疫」との関わりです。ストレスが続くと交感神経が過剰に働き、体が常に緊張状態になってしまいます。その結果、夜になっても深く眠れず、翌朝まで疲れを持ち越してしまうのです。また、免疫の働きが乱れると、軽い炎症が体のあちこちで続き、だるさや集中力低下につながることも分かってきました。
「疲労」について研究が進むにつれさまざまな視点から話題となっているものもあります。
・ミトコンドリアの働き
細胞の中でエネルギーをつくる「ミトコンドリア」がうまく働かないと、いくら休んでも体が回復しにくくなります。
・腸内環境との関係
腸は「第二の脳」と呼ばれるほど神経や免疫と深くつながっています。腸内細菌のバランスが崩れると、体だけでなく気分にも影響し、疲労感や落ち込みにつながることがあるといわれています。ヨーグルトや発酵食品が疲れに良いとされるのは、この腸内環境の研究が背景にあります。
・脳の炎症(神経炎症)
MRI研究では、慢性疲労のある人の脳内で「微小な炎症反応」が起きているケースがあることから体の疲れが単なる筋肉の問題ではなく、中枢神経系の作動とも関わっていると考えられています。
漢方では「気の不足」や「血の巡りの滞り」と考える
「心身の疲労」といっても、具体的な症状は人それぞれです。
身体症状に現れる人もあれば、精神的な不調を感じる人もいます。
これといった原因がはっきりしない場合は、漢方的な視点も体調回復のヒントとなるかもしれません。
漢方では、慢性疲労を主に「気(エネルギー)の不足」や「血の巡りの滞り」と考えます。気が不足すると倦怠感が続き、血の巡りが悪いと頭の重さや肩こりを引き起こしやすくなります。また、体の奥に冷えがあると、常に体が余計なエネルギーを消耗することとなり、回復が遅れるとされます。
慢性疲労は「休めば治る一時的な疲れ」とは違い、少しずつ積み重ねられたバランスの崩れの修復が追いつかなくなった結果ともいえます。十分な睡眠やバランスの良い食事、軽い運動が基本ですが、改善が難しい場合は医療機関や薬局で相談することも大切です。
慢性的な疲労は、生活の質を下げるだけでなく、将来的な生活習慣病やうつ症状とも関連していることがわかっています。
「我慢していればそのうち何とかなる」ではなく、「疲れは回復のための大切な体の声」と受けとめて、心身をいたわる生活をぜひ取り入れてみてください。
※このページの内容は2025年10月17日現在のものです。