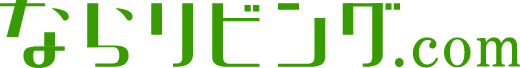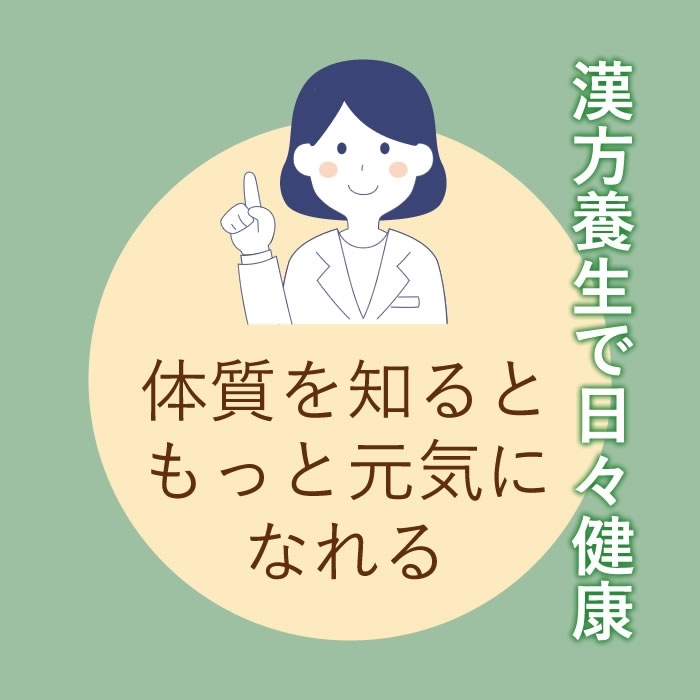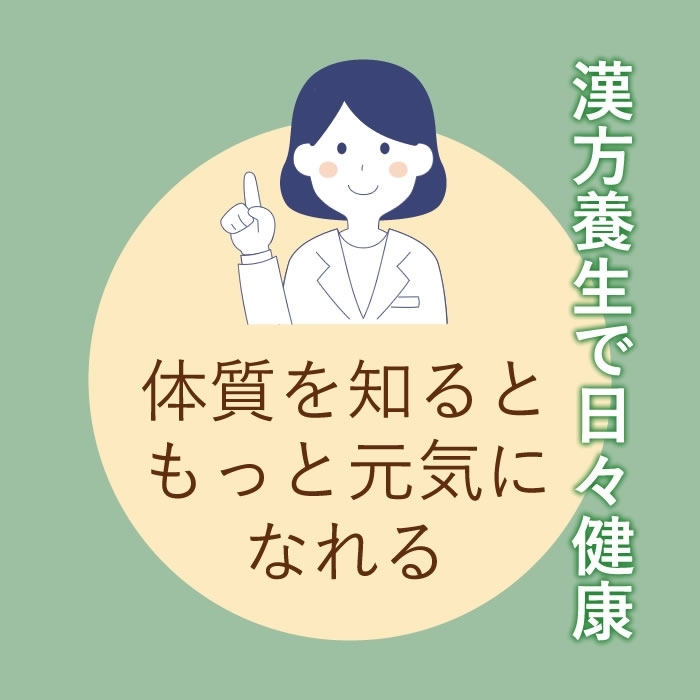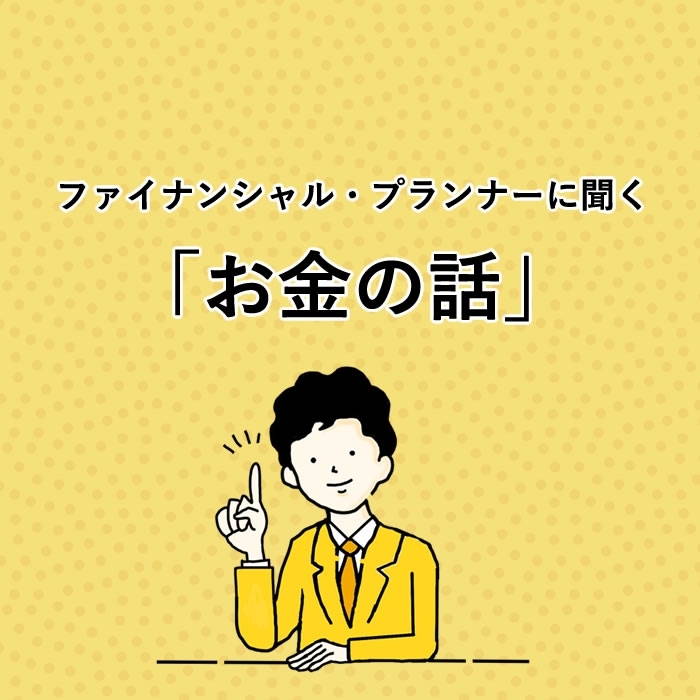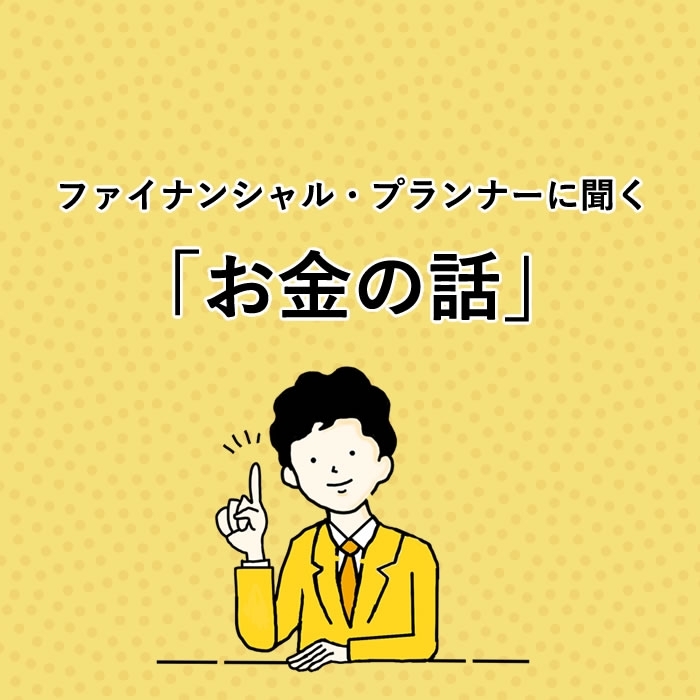漢方養生で日々健康~体質を知るともっと元気になれる~vol.47 「赤ら顔」にお悩みの方へ
漢方理論をもとに女性の悩みに応えてきた一陽館薬局のかしたに陽子さんに、健康を保つ秘訣を聞く連載企画。今回は、メイクでも隠しきれないなど深刻な悩みにもつながる「赤ら顔」についてのお話です。

顔の皮膚が慢性的に赤みを帯びた状態
季節の変わり目や寒暖差の激しい日、あるいは人前に立ったときなどに、頬がぽっと赤くなってしまう、いわゆる「赤ら顔」のお悩みが増えています。中には、常に顔の赤みが取れず、メイクでも隠しきれないという深刻な声も聞かれます。今回は、赤ら顔の要因となる体の仕組みと、タイプ別に整える方法についてご紹介します。
「赤ら顔」とは、顔の皮膚が慢性的に赤みを帯びた状態を指します。特に頬や鼻のまわりに多く見られ、一時的なものから長く続くものまでさまざまです。寒暖差や入浴、飲酒、辛いものを食べたときなどに赤みが強くなることが特徴です。
「赤ら顔」の要因は?
一時的に血流が増えただけなら自然に戻りますが、慢性的な赤みが続く場合には、皮膚や血管、あるいは自律神経の働きに関係していることも考えられます。
医学的には、赤ら顔にはいくつかの原因があるとされます。
最も多いのは、皮膚の表面近くにある毛細血管が拡張して赤く見える「毛細血管拡張症」です。紫外線や寒暖差、加齢によって血管がもろくなり、拡張したまま戻らなくなることがあります。
また、「酒さ(しゅさ)」という慢性炎症性の皮膚疾患では、顔の赤みやほてりのほか、小さな吹き出物やかゆみを伴うことがあります。体質的な要因に加え、ストレスや温度変化、刺激の強い化粧品なども悪化要因になります。
さらに、敏感肌や乾燥肌の人も注意が必要です。肌のバリア機能が低下すると、外的刺激で血流が過剰に反応し、赤みが出やすくなります。ホルモンの変化や自律神経の乱れ、更年期なども血流調整に影響するため、顔がほてりやすくなります。
漢方的な視点も参考に
皮膚科の治療では、症状や原因に応じて抗炎症薬や保湿剤の処方、レーザー治療による毛細血管の収縮などが行われます。酒さの場合は、抗菌作用のある薬や外用薬で炎症を抑える治療が中心とされます。
日常生活では、洗顔のしすぎや刺激の強い化粧品を避け、肌を乾燥させないことが大切です。急激な温度変化、長時間の入浴、辛い食事やアルコールなどは赤ら顔を悪化させることがあるため、なるべく控えるようにしましょう。
これといった原因がはっきりしない場合は、漢方的な視点も参考にしてみてください。
漢方では、要因のひとつとして「冷えのぼせ」といわれる状態が関わっていると考えます。「冷えのぼせ」とは、体の下半身が冷えているのに、上半身や顔だけ熱がこもる状態を指します。
現代の生活では、長時間のデスクワークや冷房による冷え、夜更かしやストレスなどで自律神経のバランスが崩れ、血液の流れが上半身に偏りやすい傾向がみられます。結果として、下半身が冷えて血流が滞る一方で、頭や顔に熱がこもり、顔の"赤み"や"ほてり"として現れるのです。
また、冷たい飲み物や生野菜を好む方にも「冷えのぼせ」は多く見られます。体の中心である胃腸が冷えているのに、上部だけが熱くなるこのアンバランスが続くと、顔の赤みも慢性化しやすくなります。
「冷えのぼせ」の改善法は?
冷えのぼせを改善するには、体全体の「巡り」を整えることが大切です。下半身を温め、血液と気の流れをスムーズにすることで、自然と顔のほてりも和らぎます。
食事では、しょうが、ねぎ、黒ごま、にんじん、山芋など、体を温める食材を取り入れましょう。逆に、冷たい飲み物やアイス類、夜遅くの甘いデザートは体を冷やしやすく、のぼせの悪化につながります。
また、軽いウォーキングやストレッチなどで下半身の血流を促すこともおすすめです。湯船に浸かる場合は、ぬるめのお湯で半身浴を行い、下半身を中心に温めると良いでしょう。
赤ら顔を単なる肌のトラブルとしてだけではなく、血流の乱れや冷え、ストレスなど、体全体のバランスの乱れの現れととらえ、表面的なケアだけでなく、生活習慣や体質を見直し、体の内側から整える意識をもつことが大切です。
体のめぐりが良くなると、顔の赤みだけでなく、冷えや疲れ、気分の落ち込みも次第に軽くなっていくことも期待できます。
心と体を穏やかに保ち、自然な美しさを育てていきましょう。
※このページの内容は2025年11月21日現在のものです。