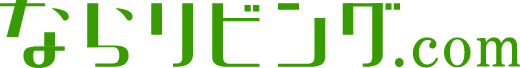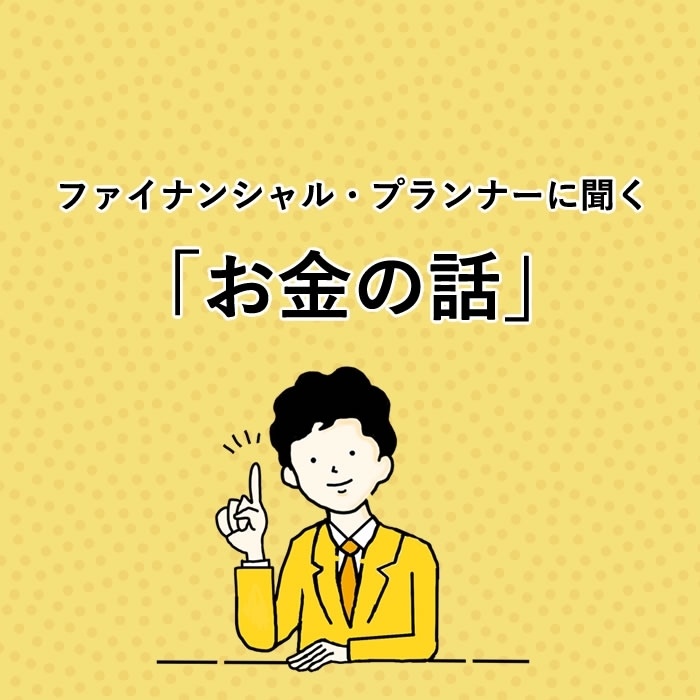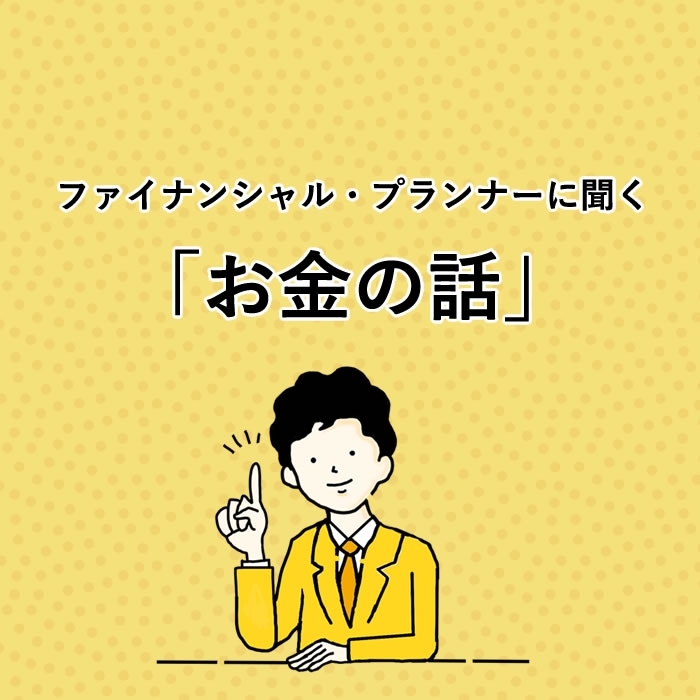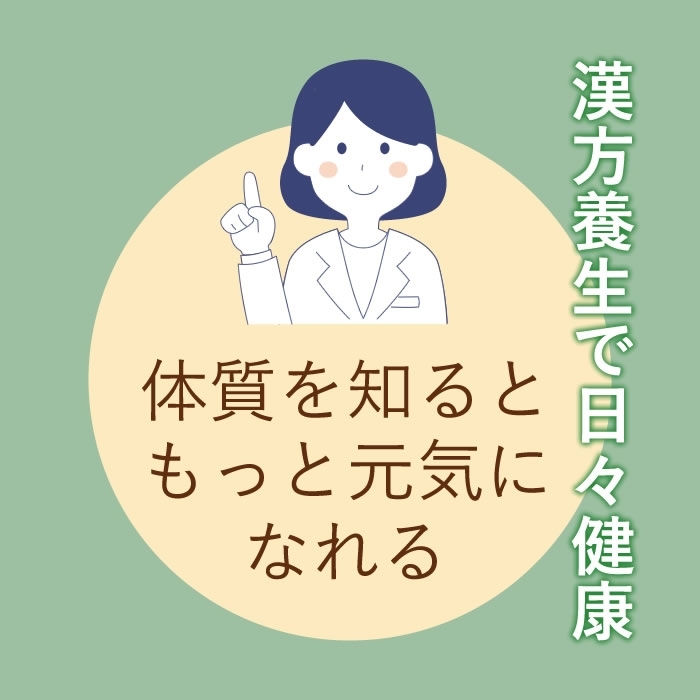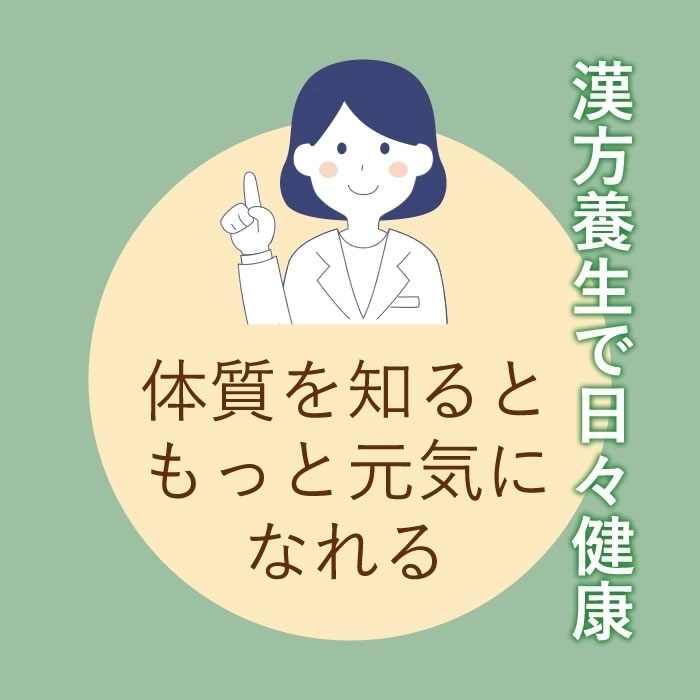ファイナンシャル・プランナーに聞くお金の話【20】「卒婚」について
誰もが気になる「お金」に関する情報を、お金のプロであるファイナンシャル・プランナーに聞く連載。今回は新しい夫婦の形態である「卒婚」にまつわるお金の話です。

新たな夫婦のカタチ「卒婚」について
最近、マスメディアなどで「卒婚」という言葉を聞くことがあるかもしれません。
卒婚とは婚姻関係を戸籍上は残したまま、夫婦がお互い必要以上に干渉せず、自由に生活することです。
2004年に杉山由美子氏が著書「卒婚のススメ」で使用した造語で、2000年代以降の日本で生まれた夫婦の新しい形態です。
卒婚しても法律上の離婚は成立しないので、扶養義務や相続権は残ります。
1.卒婚と離婚との違い
離婚は、婚姻関係を解消することから子どもや親族関係にも変化を及ぼし、世間体にも様々な影響を与えます。
卒婚は、戸籍上は婚姻関係を残したままなので、上記に対する影響は最小限に抑えることができ、夫婦それぞれ自立した自由な生活を送ることができます。
2.卒婚をしたい理由
①夫の世話から解放されたい。
②子どもが社会人として自立した。
③夫が定年退職した。
④自由に外出や旅行をしたい。
⑤趣味や仕事に没頭したい。
⑥夫婦それぞれが自立したいと感じ始めた。
3.卒婚生活をうまく過ごす条件
①妻が生活的に自立できる
卒婚するためにはお金が必要です。
法律上は、夫への生活費の請求は可能ですが、それでは卒婚の意味とは少しかけ離れると思います。
預貯金を貯めておくか、就労に就いていることが望ましいです。
②子どもが自立している
子育て中のまま卒婚をすることは、子どもの健康状態を把握したり、学校でのトラブル対応などで、働く時間や自由な時間が持てなくなるためにお勧めはできません。
③夫が自立できる
夫が自立できなければ、卒婚は成り立ちません。
④夫も自由な時間を欲しがっている
妻だけが自由を欲しがっていても卒婚は成り立ちません。
夫婦双方が、自由を満喫できなければ卒婚は継続できないでしょう。
4.卒婚における生活費や年金について
(1) 卒婚の生活費分担
①どちらかが生活費のすべてを負担する。
②卒婚前に財産分与する。
③住居費に関しては名義人負担とし、生活費はそれぞれが負担する。
④おのおのが生活費を負担する。
卒コンにおける生活費や年金について、上記のパターンはありますが、卒婚においては基本的におのおのが負担することがうまくいく条件だと思います。しかし夫婦ごとに形はあると思いますので、相談して事前に決めておくのがいいと思います。
(2) 老後資金について
人生100年時代と言いますが、老後資金も生活費と同じように夫の年金の分配を期待するのではなく、働いているうちに老後資金を貯めておくことをお勧めします。
老後資金も自前ということが、自立への第一歩です。
☆ ☆ ☆
最後に、卒婚は事前にルール化しておくことが重要です。
自由が一番と言っても、何でもありという訳では卒婚生活はすぐに破綻するでしょう。
お金について、NG事項について、万が一の場合についてなど、あまり窮屈にならない程度でルール化しておくことが大切です。
【情報提供】
独立系FP事務所 セントラルパートナーズ代表
筒井博之さん
★ならリビングでは、家計についての相談を受け付けます。
詳細はこちらをご覧ください。
「ファイナンシャル・プランナーに聞くお金の話」過去の話はこちらから
※このページの内容は2023年8月11日現在のものです。