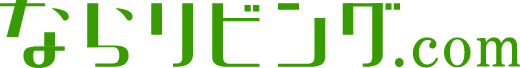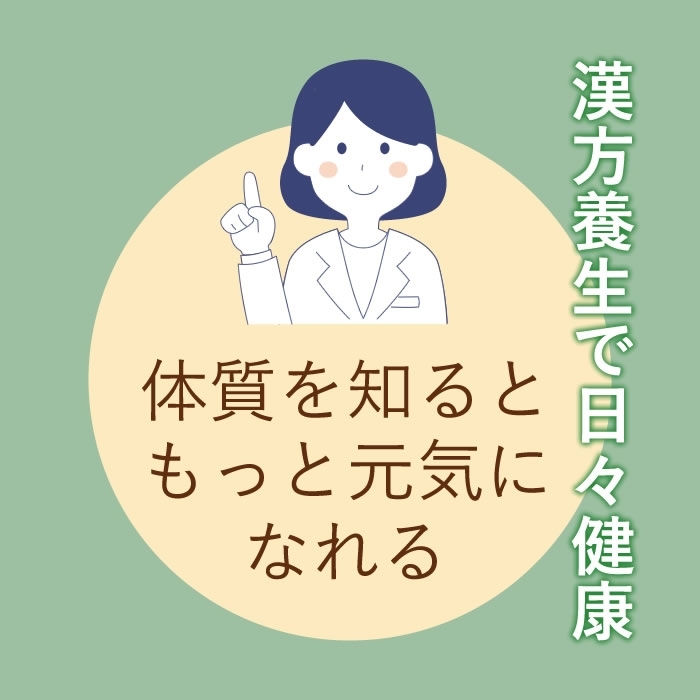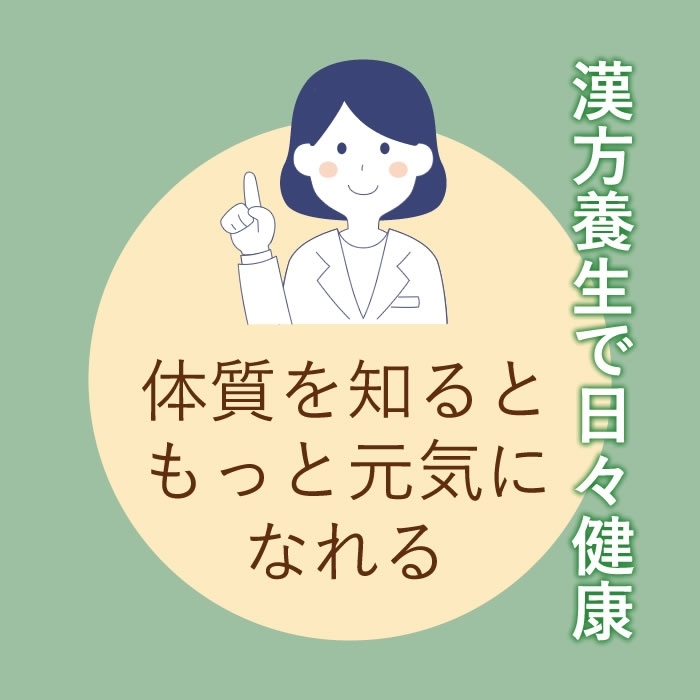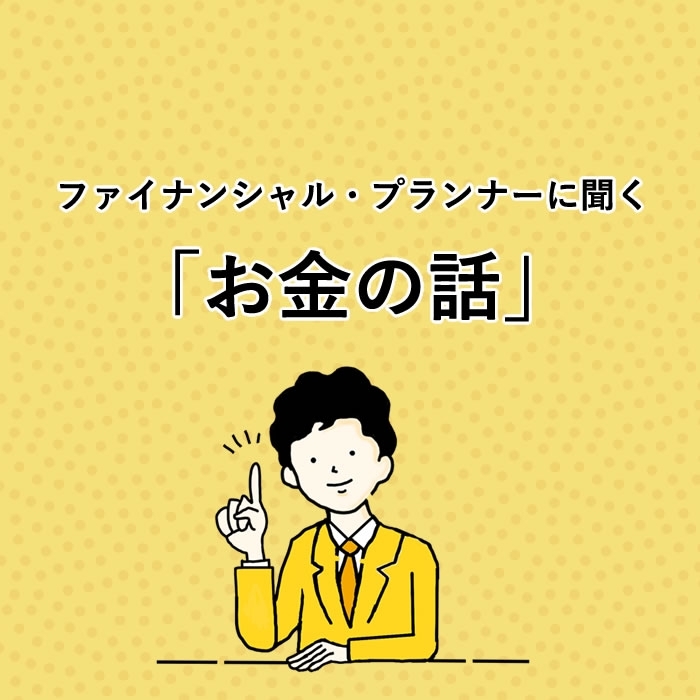漢方養生で日々健康~体質を知るともっと元気になれる~vol.33「口内炎」にお悩みの方へ
漢方理論をもとに女性の悩みに応えてきた一陽館薬局のかしたに陽子さんに、健康を保つ秘訣を聞く連載企画。今回は多くの人が一度は経験している、「口内炎」についてのお話です。

口内炎はさまざまな体調を表すサイン
「口内炎」は多くの方が一度は経験がある症状ではないでしょうか。
ちょっとかんだだけなのにとても痛くなったり、忙しくてつい不摂生になって抑えがきかず悪化したりしたことはありませんか。
体質的に起こりやすいタイプもありますが、病気が原因でない場合は大半が「ライフスタイル」にあると言えるほど身近に起こりやすいトラブルかもしれません。
しかし、いったんできてしまうと痛みなどで食事がとりづらい、熟睡できない、仕事や勉強に集中できないなど、生活面ではストレスにもなりかねません。
口内炎は、さまざまな体調を表すサインとしてとらえ、対処していくことも大切です。
口内炎とは
口内炎とは、口の中やその周辺の粘膜に起こる炎症をいいます。
頬の内側や舌、唇など口の中ならどこにでもできる可能性がありますが、痛みや炎症の程度も人それぞれです。原因もさまざまでストレスや栄養不足などによる免疫力低下や、口の中をかんでしまうなどの物理的刺激、ウイルス感染などのほか、原因がはっきりしない場合もあります。病気の症状のひとつとして起こる場合もあるので、注意が必要です。
通常は数日ほどで自然に治るものですが、対処のタイミングを逃すと、ひとつだけではなくいくつもできたり、悪化してしまって治るまでに時間がかかることもあり、放置しないで早めに対策をとることをおすすめします。
口内炎ができやすい部位としては、頬の内側や歯ぐき、舌、唇や口蓋、のどの周辺などで、部位によって、歯ぐきの場合は「歯肉炎」、舌にできたものは「舌炎」、唇や口角では「口唇炎」「口角炎」と呼ばれます。
口内炎の症状は、痛みや腫れ、ただれや出血などですが、軽度なものから重度なものまでさまざまです。でき始めは粘膜に米粒程度の白いただれが起こり、その周囲が赤く腫れて痛んだりしみたりし始めます。患部の炎症が続くと、粘膜の表面がただれてびらん様(皮膚や粘膜が破れた状態)になり、ただれた部分がえぐられ、口内炎ができます。
口内炎の種類は症状や原因によってさまざま
口内炎の種類は症状や原因によってさまざまです。もっとも一般的な口内炎は「アフタ性口内炎」で頬の内側や舌、唇の裏や歯ぐきにできやすく、痛みがあり、食べ物がしみます。女性の場合は、生理前や妊娠期などホルモンバランスの乱れや体力を消耗しやすい状況でもできやすくなります。
入れ歯や矯正器具、熱い食べ物などが粘膜と接触し、刺激を受けた部位に傷ができて細菌が繁殖することで発症する「外傷性口内炎(カタル性口内炎)」は刺激の強い食べ物にしみたり、ヒリヒリとした痛みを感じやすくなり腫れなどにより味覚が鈍ってしまうこともあります。全体的に赤く腫れて熱を持ち、口の中が荒れた状態になるので、口内炎と気づかない場合も多いようです。
生後6カ月~3歳くらいの乳幼児に多いウイルス性口内炎である「ヘルペス性口内炎」はヘルペスウイルスへの感染により発症します。舌や唇、歯ぐきだけでなく、唇の外側やのどに近い粘膜など、いたるところに現れることがあります。水疱ができて赤く腫れ、強い痛みや高熱を伴うこともあります。一度感染するとウイルスを保持してしまうため、大人になっても、抵抗力などが低下した場合など発症しやすくなります。
もともと自分の口の中に存在している常在菌であるカンジダというカビ(真菌)が原因となる「カンジダ性口内炎」は、健康な状態にある人が発症することはあまりなく、ステロイド剤を長く服用していたり、糖尿病や血液の疾患、ガンなど他の病気を患っている方や、乳幼児や高齢者、妊婦など体力や抵抗力が弱い方がかかりやすいもので、抗生物質の長期服用によっても口内の常在菌のバランスが崩れ、菌交代現象を起こすことで発症する場合もあります。
その他、特定の食べ物や薬物、金属が刺激となってアレルギー反応を起こす「アレルギー性口内炎」、喫煙の習慣により口の中に有害物質が蓄積し長期間熱にさらされることで乾燥し軽い火傷の状態が続くため起こる「ニコチン性口内炎」などもあります。
口内炎は、その種類によって対処法に違いがあります。数日で自然治癒するものもあれば、重大な疾患を併発している可能性もあるため、患部の色(赤い、白いなど)や状態(硬い、柔らかいなど)、発熱や倦怠感など、全身症状の有無、白斑や、白い苔のようなものがあるか、また再発を繰り返すなどチェックしておくことも大切です。
原因に合わせて適切な対処を
口内炎ができやすい方は、原因に合わせて適切な対処をすることが改善につながります。
栄養バランスや生活習慣の乱れによるのか、歯みがきやあわない義歯、やけどなどの傷によるのか、加齢やからだの不調、薬による影響なのかなども見直してみてください。
はっきりとした原因ばかりでなく、精神的な疲れやストレスも原因となります。
口の中の粘膜は、常に新しく生まれ変わっていますが、疲労の蓄積や睡眠不足が続くと代謝が滞り、粘膜の再生や修復がうまくいかず荒れやただれ、潰瘍ができやすくなります。
また、加齢やストレスは唾液の減少につながり口の中が乾燥し、口内炎ができやすい環境といえます。唾液は汚れを洗い流して清潔にするだけでなく、粘膜の保護や修復をする役目があり口内環境を正常に保つためにも重要な働きを担っています。
慢性的な疲労やストレスによる免疫力低下には漢方もおすすめです。
漢方では、口内炎は胃熱とも言って、胃に熱がこもった状態ととらえます。
季節性もあり、夏の暑さと夏バテが重なり抵抗力が落ちている初秋の頃は空気の乾燥も始まり、口内炎が起こりやすい時期といえます。
体質的に、乾燥しやすい、熱がこもりやすい、胃が弱いタイプは健康のためにも体質に合った漢方薬などで養生されるのも対策のひとつです。
ちょっと無理が続いているな、食生活が乱れているな、と感じたら早めに休養をとり、口内炎に悩むことのない健康な日々を取り戻しましょう。
※このページの内容は2024年8月23日現在のものです。