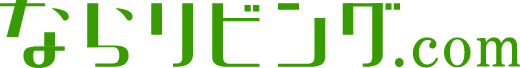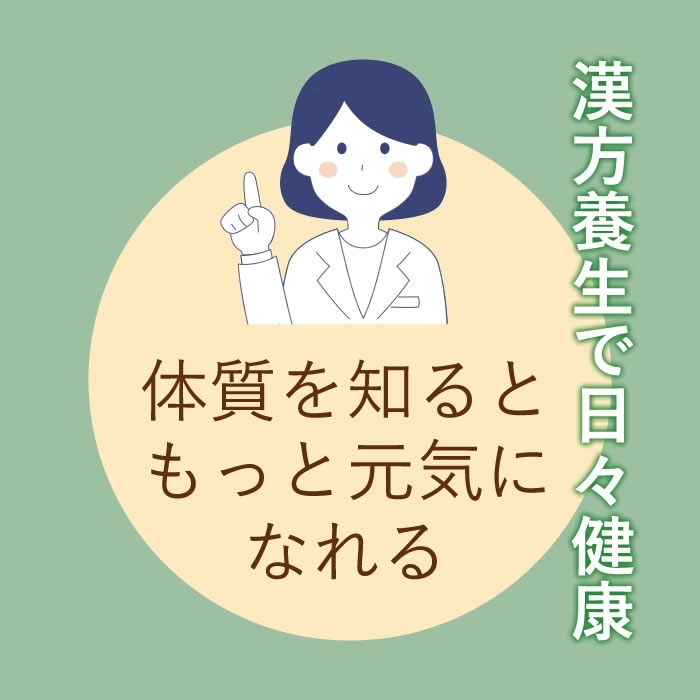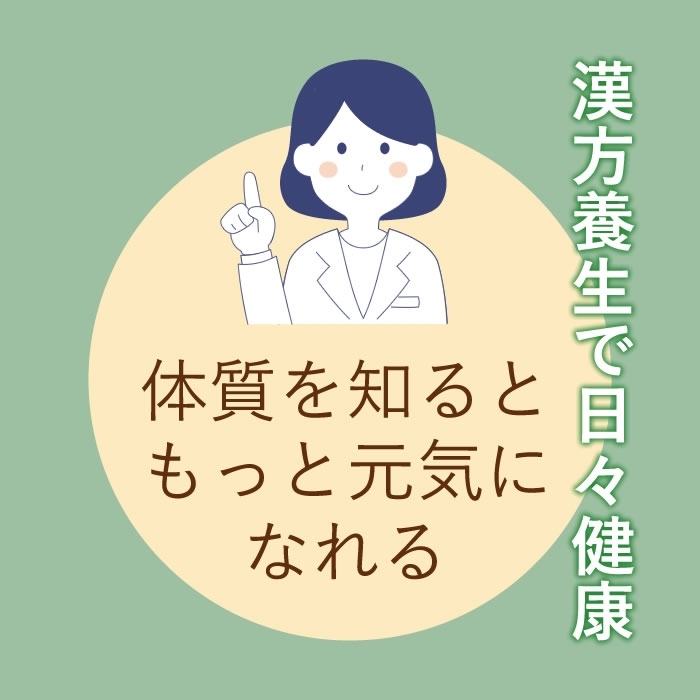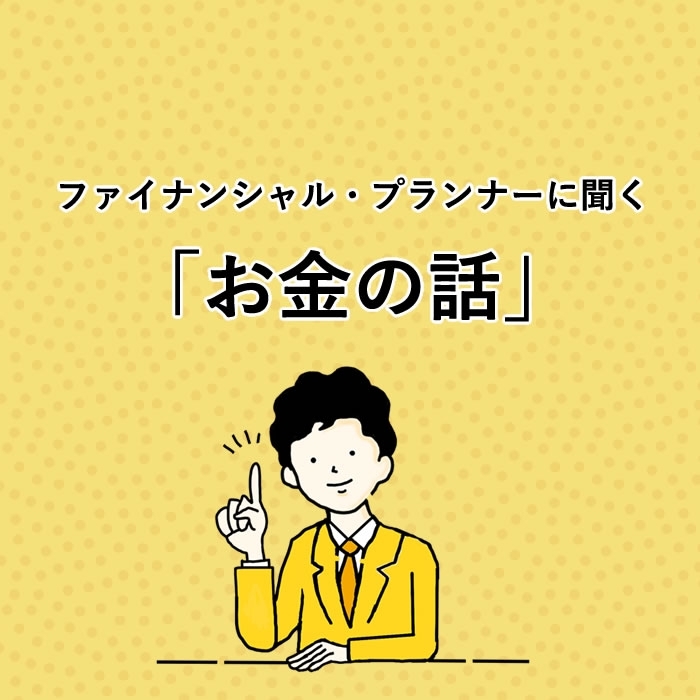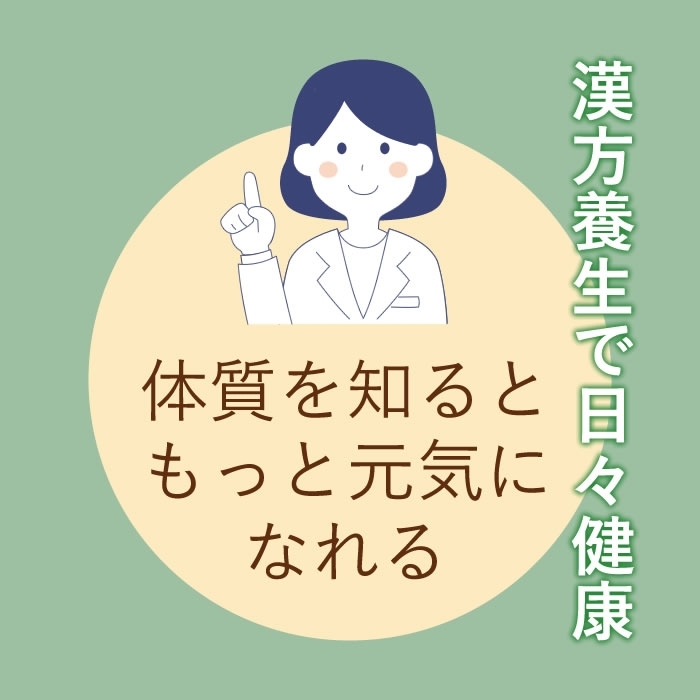漢方養生で日々健康~体質を知るともっと元気になれる~vol.43 「胃腸症状」にお悩みの方へ
漢方理論をもとに女性の悩みに応えてきた一陽館薬局のかしたに陽子さんに、健康を保つ秘訣を聞く連載企画。今回は、胃の不調を感じるのに、病院では「異常なし」といわれることも多い、機能性ディスペプシアについてのお話です。
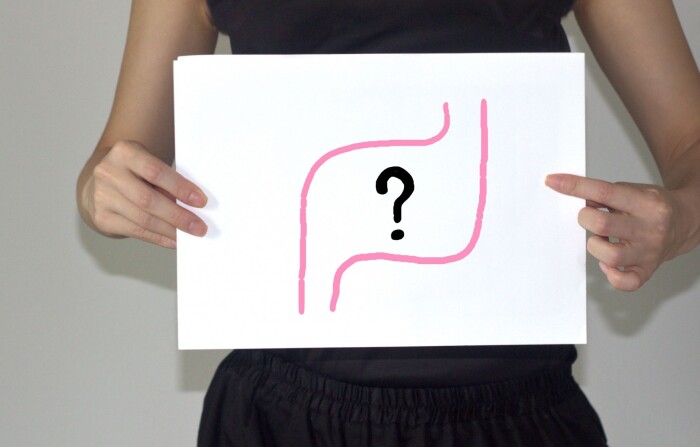
胃がつらいのに原因が見つからない?
~機能性ディスペプシア~
「食後すぐにお腹が張る」「みぞおちが痛い」「少し食べただけで満腹になる」こんなにも"胃の不快感"が続いているのに、病院で検査をしても「異常なし」と言われたことはありませんか?
胃の痛み、胃もたれといった不快感が続くと、仕事に集中できない、勉強に身が入らない、病院に行くために仕事を休まなくてはならないなどの悩みにもつながるのではないでしょうか。
機能性ディスペプシアは、明確な器質的な異常(胃潰瘍や胃がんなど)が見つからないにも関わらず、慢性的に胃の不調を感じる病態です。
症状は大きく二つのタイプに分かれます。
ひとつは「食後の膨満感や早期満腹感」が目立つタイプ、もうひとつは「みぞおちの痛みや灼熱感」が強いタイプです。これらは単独、あるいは混在して現れることもあります。
日本では、約10人に1人、胃の不調で病院を受診する人のうち、実に半数以上がこの病態に該当すると言われています。
胃の検査で異常がないため、胃腸虚弱の人、胃の不調としてやり過ごしがちでしたが、胃の調子が悪くて食べたくない、外に出たくない、楽しくない、など生活の質や労働生産性の低下を招くことから、治療すべき病気として認識が高まっています。
機能性ディスペプシア(Functional Dyspepsia : FD)とは
胃の痛み、胃もたれ、胸やけ、吐き気などの症状が慢性的に続いているのに、病院で内視鏡検査を含む検査を行っても異常が認められないもので、機能性胃腸症と呼ばれることもあります。以前は、いわゆる「神経性胃炎」や「ストレス性胃炎」といわれたり、慢性的な炎症がないにもかかわらず「慢性胃炎」と診断されたりしていました。
自覚症状があっても炎症やその他の異常が確認できない病気として、非びらん性胃食道逆流症や過敏性腸症候群がありますが、それぞれ異なった特徴を持つ病気とされています。
・非びらん性胃食道逆流症
食道(胸の上部)に不快感が生じる
・機能性ディスペプシア
胃(おなかの中心あたり)やみぞおちに不快感が生じる
・過敏性腸症候群
大腸の機能障害で、下腹部の不快感や下痢の症状が現れる
医学的な診断と治療
診断は、まず胃カメラ(上部消化管内視鏡)などで、潰瘍やがんなどの器質的疾患がないことを確認します。そのうえで、わずらわしい食後のもたれ感(膨満感)、食べ始めてすぐに満腹になってしまう早期満腹感、みぞおちの痛み、みぞおちが焼けるような感じの4つのうちの1つ以上が3ヵ月以上続いている場合、日常生活に支障がある状態が機能性ディスペプシアと診断され、症状の内容、タイミング、頻度などによって、分類されます。
治療としては、症状に応じて消化管運動促進薬や胃酸分泌抑制薬が用いられますが、すぐに効果が出るとは限りません。心理的要因が強い場合は、抗不安薬や抗うつ薬が処方されることもあります。
原因
この症状を引き起こす原因はひとつではなく、さまざまな要素が複雑に関わっていると考えられています。
胃運動機能異常(胃が十分に動かず、食べたものをうまく十二指腸に送ることができないこと)や、胃酸過多(胃酸の出過ぎ)、胃の知覚過敏(わずかな刺激でも反応してしまう状態)、ストレス、ピロリ菌への感染などがあげられますが、まだはっきりと特定されていません。
加えて、ストレスや不安といった心理的な要因も見逃せません。生活の中で不安があったり、睡眠不足、忙しい、季節の変わり目などストレスで自律神経のバランスが乱れると、胃の働きが鈍くなったり過敏になったりします。睡眠不足や過労、暴飲暴食などの生活習慣の乱れも、症状を悪化させる要因となります。
漢方薬による体調管理も
機能性ディスペプシアは、自律神経に制御されている胃の働きが、ストレスによる自律神経の乱れによって調子を崩すことが原因の一つと考えられており、ストレスを感じやすい人や疲労を感じやすい人に起こりやすいと言われていることから、漢方薬による体調管理もおすすめです。
漢方では、胃の不快感は「脾胃(ひい)の虚弱」や「肝気(かんき)のうっ滞」「痰湿(たんしつ)」といった体質的要因が絡んでいると捉えます。
例えば、ストレスや緊張によって胃の働きが悪くなるタイプは、「肝気犯胃(かんきはんい)」といい、気の流れを整えることで症状緩和を目ざします。
また、胃腸がもともと弱く、食が細く、冷えやすい人には、脾を補い胃の働きを助けるよう働きかけ、食後に膨満感が強い場合やゲップ・胃もたれが目立つ場合は、湿邪をさばく処方なども利用します。
一人ひとりの体質や症状の出方に合わせて、オーダーメイドで選ぶことが大切だと思います。
生活習慣の見直しも
薬に頼りすぎず、胃の調子を整えるために、自分でできる対策として日々の生活習慣を見直すことも大切です。
特に重要なのは、胃に負担をかけない食べ方です。早食いは胃に負担をかけるため、ゆっくりよくかむように心がけ、お腹いっぱい食べずに腹八分目を意識しましょう。
また、自律神経の働きを高めて、自律神経の調子を元に戻すことも大切です。そのためには、十分な睡眠をとり、ウォーキングなど適度な運動を心がけ、禁煙することも大事です。
そして何より、ストレスを上手に逃がす工夫を心がけてみましょう。深呼吸やストレッチ、散歩や趣味の時間を取り入れることで、自律神経のバランスが整い、胃の不調もやわらぐこともあると思います。
機能性ディスペプシアは、目に見える異常がない分、周囲からも理解されにくく、ご本人にとってもつらい病態です。
ゆったりと体の声に耳を傾け、不調をきっかけに「こころ」と「からだ」のバランスを見つめ直すことから始めてみましょう。ご自身に合ったケアを続けることで、快適な毎日を取り戻すことができるのではないでしょうか。
※このページの内容は2025年7月18日現在のものです。