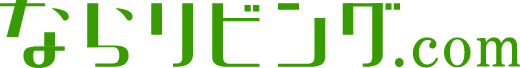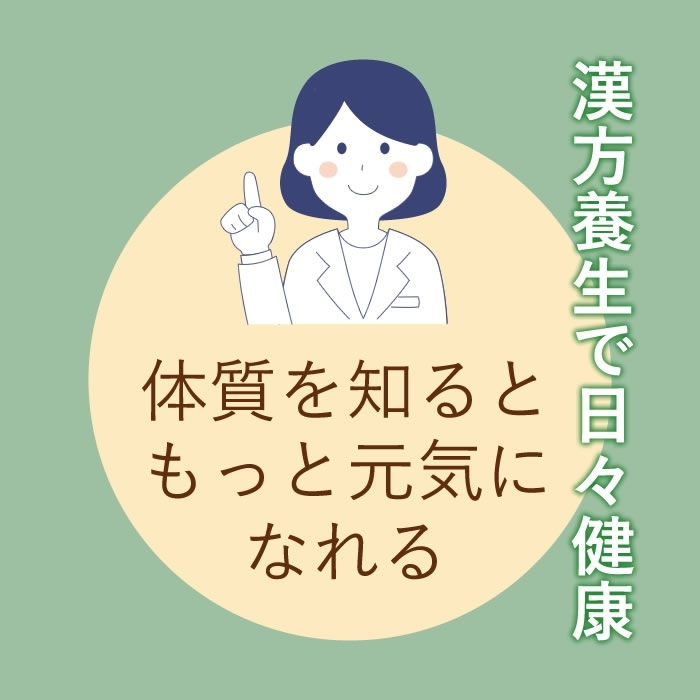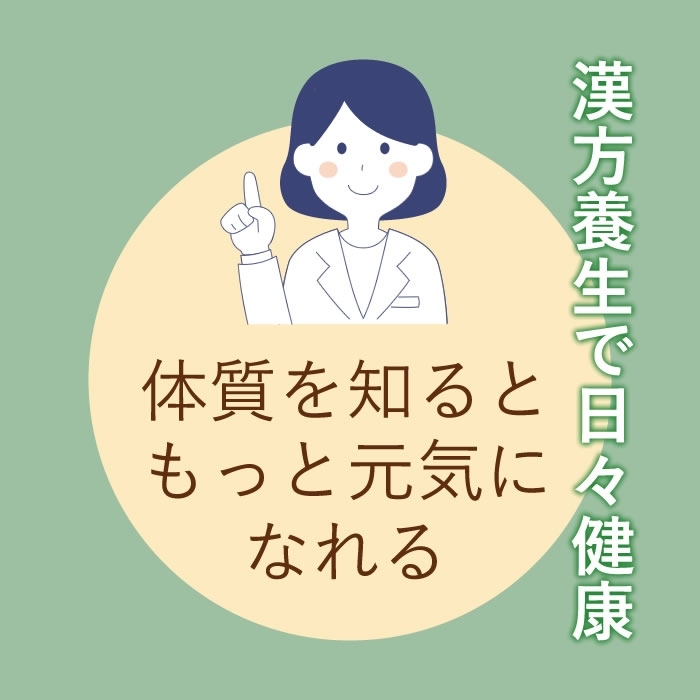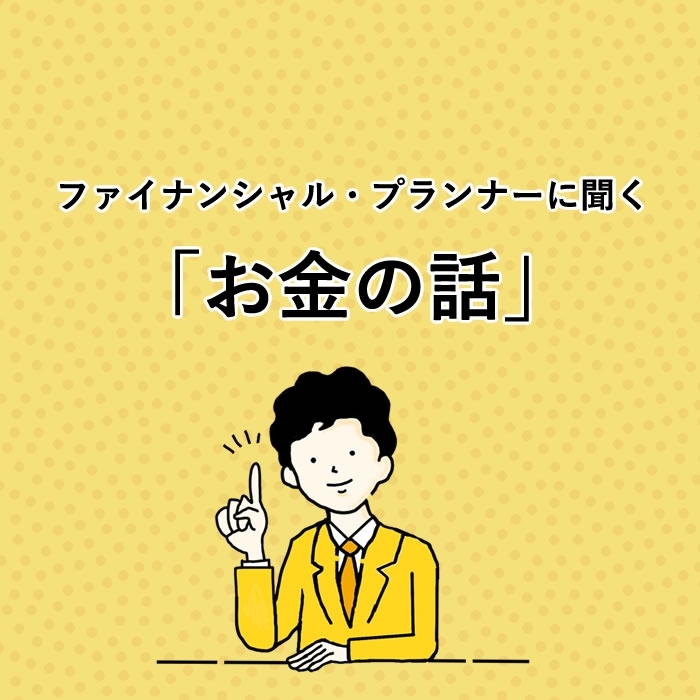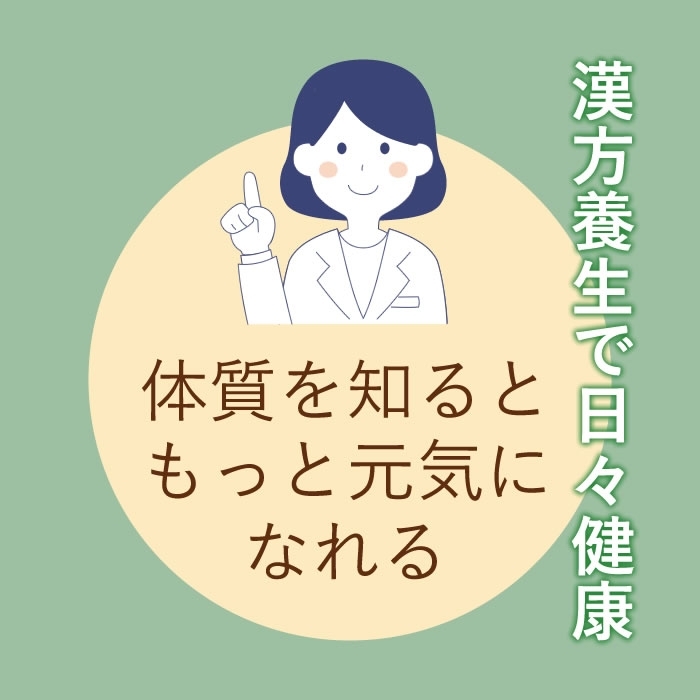漢方養生で日々健康~体質を知るともっと元気になれる~~vol.34「長引く咳」にお悩みの方へ
漢方理論をもとに女性の悩みに応えてきた一陽館薬局のかしたに陽子さんに、健康を保つ秘訣を聞く連載企画。今回はこれからの季節にも悩む人が多い、「長引く咳」についてのお話です。

原因見極め適切な対策を
人前で気になる症状のひとつに「咳」があげられます。
皆さんは、どんな時にどんな咳が出ますか?
ウイルスや細菌などの感染、花粉や異物による刺激、寒暖差や乾燥や湿度など気象の影響など、さまざまな咳は、空気の通り道である気道に侵入した異物を追い出すために起こるからだの防御反応でもあります。
外的要因以外にも、精神的なストレスを感じた時や高齢になって体力低下により出る咳もあります。
咳がなかなか止まらないと、夜も咳込んで眠れなくなったり、体力を消耗してしまう、など体調の回復をさらに遅らせることになってしまう場合もあります。
しかし、咳は異物を排除するための反応ですから、単純に薬で止めればよいというものではなく、咳が出る原因を見極め適切な対策をとることも大切です。
一般的には、風邪の治りかけやこじらせた場合に長引くことが多く、安静にしていれば自身の免疫機能が働くため自然に治りますが、2~3週間経っても治まらない場合や眠れないほど激しい咳が続く場合は、病気の可能性もあります。
咳の原因は
咳の原因としては、感染症、アレルギー、タバコやほこりによるものがあげられます。
◎感染症:風邪、急性気管支炎、肺炎、結核など
特に結核は日本では毎年約12,000人が新たに発症し、毎年約1,900人が亡くなっており政府広報からも「古くて新しい病気」と警告されています。
◎アレルギー:気管支喘息、咳喘息、花粉症など
咳喘息は喘息の前段階の状態で、日本では90万人以上が喘息の治療を受けています。
◎タバコなど有害物質によるもの:COPD(慢性閉塞性肺疾患)
慢性閉塞性肺疾患(COPD)とは、以前には慢性気管支炎や肺気腫と呼ばれてきた病気の総称です。
◎その他:肺がん、喉頭がん、心不全、胃食道逆流症、後鼻漏、大動脈瘤、薬の副作用など
病院では咳の治療は、痰の有無や色、乾いた咳か、湿った咳かといった咳の様子、いつから、どのような時に出るかなどの情報をもとに検査や投薬が行われます。
漢方では体内の水分バランスを整える療法も
漢方は風邪や咳にも日常的に用いられています。
咳は湿度が低く空気が乾燥すると出やすくなるように、水分の影響を受けやすいと考えられます。
咳が出るのは何らかの要因で、体内の水分バランスの不調や気管支など粘膜の潤い不足が根底にあります。
漢方での咳の治療は、症状を抑える「対症療法」と並行して体内の水分バランスを整える「根本療法(原因療法)」を行うと効果的です。
そのため加齢にともなう体力低下やストレスによる咳に対しても、心=こころの状態(気のめぐり)も含め全体のバランス整えることで対応することができます。
今年はオリンピックが開かれましたが、オリンピックイヤー(4年周期で)に流行する感染症といわれる「マイコプラズマ肺炎」というものも聞かれたことがあるのではないでしょうか。
マイコプラズマは軽い風邪症状から肺炎まで呼吸器症状を引き起こし、初期症状は、一般的な風邪と区別できないため早期に発見するのは難しいようです。
秋の食材活用して季節に合わせて体づくりを
食材では、呼吸器系(気管支や肺)に潤いを与えるものがおすすめです。
漢方五臓では肺は秋と関係が深いので、秋の食材を活用しましょう。
れんこん、大根、かぶ、山芋などの根菜、エリンギ、白きくらげなどのキノコ類、百合根、ぎんなん、梨など季節の味覚を中心に取り入れると季節に合わせた体づくりができます。
病気の予防をするあまり、かえって抵抗力が落ちてしまったと聞かれます。日ごろから規則正しい生活リズムを心がけることで自律神経のバランスを整え、しっかり睡眠をとることで疲れをためこまないようにして、さまざまな刺激や変化にもうまく適応できる状態を保ちたいですね。
※このページの内容は2024年10月18日現在のものです。