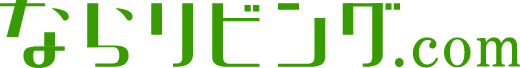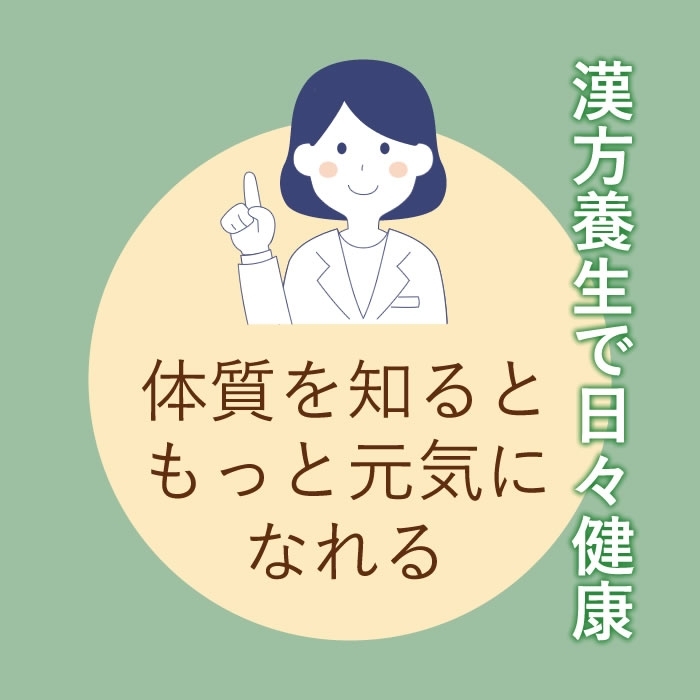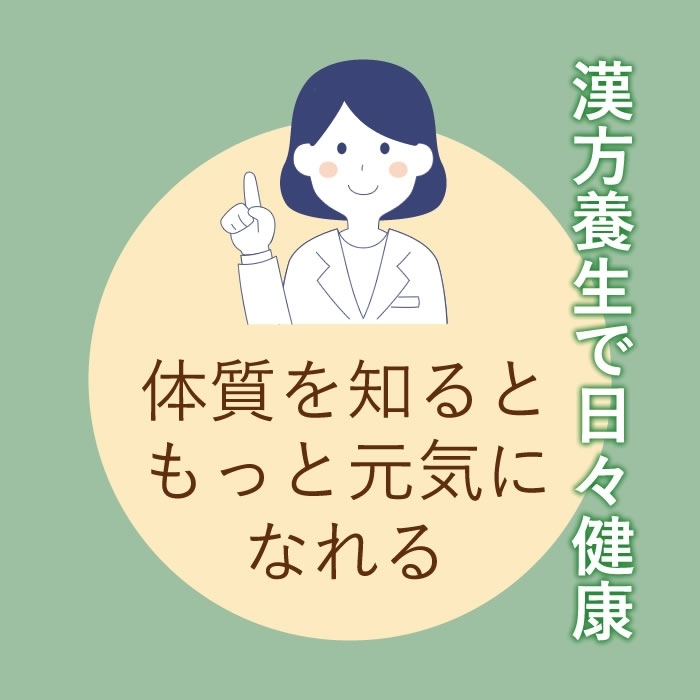漢方養生で日々健康~体質を知るともっと元気になれる~vol.38「衰え」にお悩みの方へ
漢方理論をもとに女性の悩みに応えてきた一陽館薬局のかしたに陽子さんに、健康を保つ秘訣を聞く連載企画。今回は誰もに訪れ、避けることはできない「衰え」についてのお話です。

心も体も充実した毎日を
健康と要介護状態の中間「フレイル」
できていた事がいつの間にかできなくなっている……日々の小さな変化にはなかなか気づくことができないものですが、超高齢化社会の日本では「フレイル」(2014年5月に日本老年医学会が考案)と呼ばれる高齢者における「虚弱」な状態が注目されています。年齢とともに足腰の筋力が衰えて、立って歩くのも一苦労といった "老化現象"といわれてきた状態のことです。
加齢によって身体的、精神的、社会的な機能が低下した、健康と要介護状態の中間にある状態を指し、適切な対策をしないと、転倒や寝たきり、認知症、さらには要介護状態へと進行するリスクが高まると考えらえています。
一定年齢を過ぎた分だけの「衰え」は避けられないものですが、65歳以上の「フレイル」の有病率は、前段階である「プレフレイル」の割合を含めると約半数が該当するという報告もあります。
「フレイル」によるさまざまな機能低下
フレイルには身体的な虚弱だけでなく、認知機能の低下やうつといった精神心理的なフレイル、貧困や独居など社会的なフレイルといった3つの要素も含まれます。その中で最も大きな問題となるのが、身体的なフレイルです。寝たきりの原因について65歳以上を5歳刻みで調べていくと、後期高齢者 (75歳以上) では、『高齢による衰弱』が最多で、次に『認知症』、『骨折・転倒』が増えます。
1・加齢による主な身体機能の低下
・筋力と柔軟性の低下
筋肉量が減少し、動きが遅くなったりバランスを崩しやすくなります(サルコペニアと呼ばれる現象)。
・骨密度の低下
骨がもろくなり、骨粗しょう症のリスクが高まります。転倒による骨折の危険性も増します。
・心肺機能の低下
心臓や肺の働きが弱まり、持久力が低下します。また、息切れしやすくなることがあります。
・感覚器官の変化
視力、聴力、味覚、嗅覚などの感覚が鈍くなる傾向があります。特に、白内障や加齢性難聴が一般的です。
・代謝の低下と体重の変化
代謝が低下し、太りやすくなる場合がありますが、逆に食欲減退によってやせる場合もあります。
・免疫力の低下
病気に対する抵抗力が弱まり、感染症や慢性疾患にかかりやすくなります。
2・認知的・精神的な衰え
・記憶力の低下
特に短期記憶が弱くなり、忘れ物や物忘れが増えることがあります。
・判断力や学習能力の低下
新しい情報の習得や複雑な判断に時間がかかる場合があります。
・注意力の低下
一度に複数の作業をこなす能力が低下することがあります。
・感情の変化
孤独感、不安、うつ状態が増えることがあります。社会的つながりが減ることで悪化する場合もあります。
・認知症のリスク
アルツハイマー病や血管性認知症などの疾患が発生する可能性が高まります。
3・社会的な側面の変化
・社会的孤立
退職や家族構成の変化(子どもの独立、配偶者の死去など)により、社会的なつながりが減少することがあります。
・役割喪失感
現役を引退し、社会的な役割が変化することで、自分の存在意義を感じにくくなる場合があります。
・サポートの必要性
身体的、認知的な変化により、日常生活で他者の支援を必要とすることが増える場合があります。
フレイルチェック
3つ以上の項目があてはまると、フレイルと診断されます。
□体重減少 (1 年で体重が4.5kg 以上、または5%以上自然に減少)
□疲労感(何をするのも面倒だと週に3~4日以上感じる)
□筋力の低下(握力が利き手の測定で男性26kg 未満、女性18kg 未満の場合)
□歩行スピードが遅い(1m/秒未満の場合)
□身体活動が低い
筋肉が減る「サルコペニア」
フレイルには特に筋肉が関わっており、筋肉が減ることを「サルコペニア」といいます。
サルコペニアには、加齢による「一次性」と、栄養障害や身体を動かさない、運動不足による廃用性が「二次性」です。年をとるとなぜ筋肉が減少するのか、そのメカニズムについて注目されているのが「炎症」です。老化は慢性の炎症だという考え方があります。
急性の炎症といえば発熱ですが、そうではなくてもっと静かな炎症が老化を進めるというのです。
炎症によって出てくるさまざまな生理活性物質が、一次性のサルコペニアにも関与しているのではないかといわれ、老化の炎症説が注目されています。サルコペニアと診断される人は、80代前半で女性35%、男性40%、80代後半では女性50%、男性70%にのぼります。
かむ機能や飲み込む機能、そして滑舌が低下してきたり、食べこぼしが増えてくるなど、口腔機能がささいなレベルで色々と低下してきた状態を「オーラルフレイル」といいます。
飲み込みに関する筋肉の筋力低下が起こると、飲み込む機能が低下して食べたものや飲んだものが気管に入り、ムセたり、詰まったりする誤嚥を起こすこともあります。
特にお餅やこんにゃくゼリーなどを喉に詰まらせるなど、死亡原因ともなり大変危険です。
食事や運動、漢方でも対策を
対策として、栄養面では、良質なたんぱく質を適切な量を摂りましょう。
(1 日摂取目安量 成人男性:60g 成人女性:50g)
主な食品のたんぱく質含有量
木綿豆腐80g→6g
絹こし豆腐80g→4g
納豆1P40g→6g
白身の魚60g→12g
青魚60g→12g
赤身の魚60g→18g
鶏・牛・豚肉60g→12g
卵1 個→6g
「骨や歯をつくる」カルシウムもしっかり摂取しましょう。
筋肉や神経などの働きを正常に保つためにも重要な役割を担っています。
小魚、海藻、大豆および大豆製品、緑黄色野菜に含まれています。
「骨や筋肉を強くする」ビタミンDは日光浴によって皮膚でも作られ、魚、きのこ、卵などに多く含まれます。最近では、ビタミンD が少ない人はフレイルになりやすいという研究データも出ています。
運動は、散歩や室内でのスクワット、軽いダンベル運動などできる範囲の運動を心がけましょう。
昔から漢方では「老化」を「腎虚」といい、加齢による衰えを「補腎薬」というもので日ごろから補う習慣があります。男性は8の倍数、女性は7の倍数の年齢ごとに体調の節目を迎えるとされ、その世代に応じて補腎をすることで健康を維持してきました。
衰えは病気ではありませんが、衰えにより体力や気力が減退し病気にかかりやすくなります。老化を止めることはできませんが、できるだけ心も体も充実した毎日が過ごせるようサポートすることができますので、少し気になり始めたらご相談いただければと思います。
※このページの内容は2025年2月21日現在のものです。