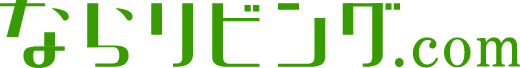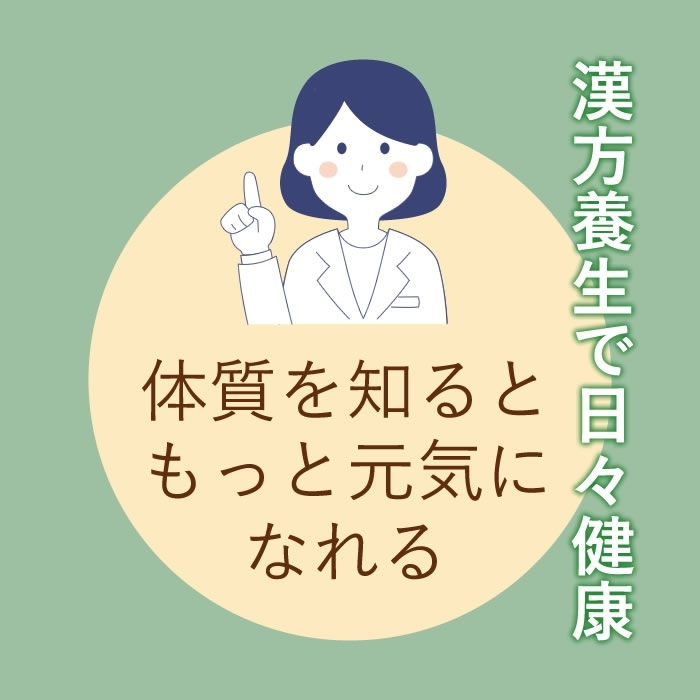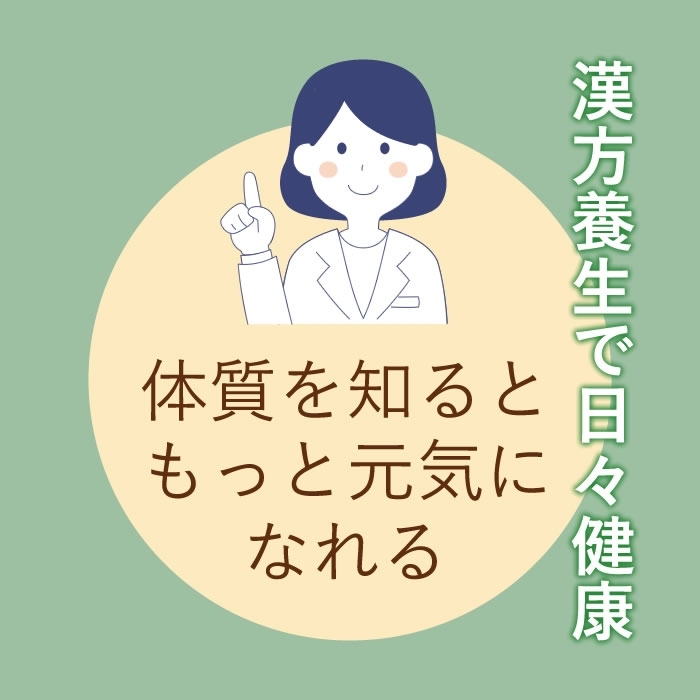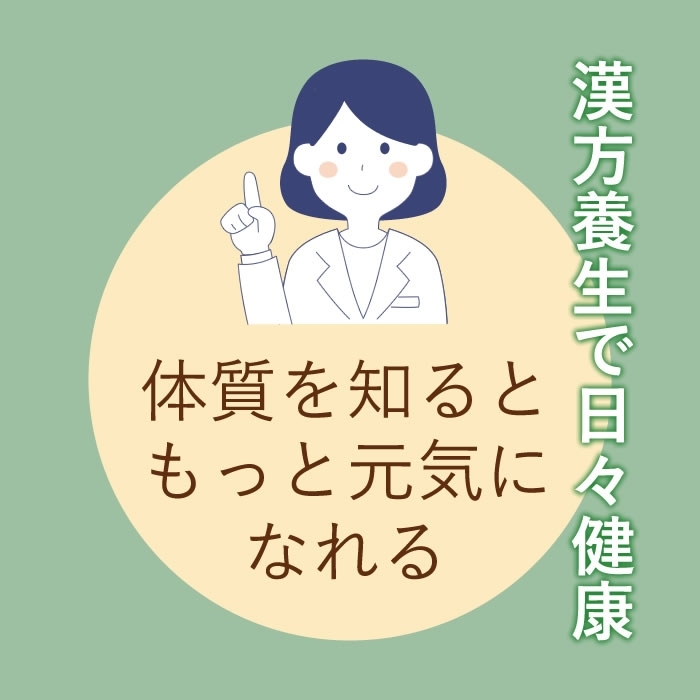漢方養生で日々健康~体質を知るともっと元気になれる~vol.40 「腸内環境」にお悩みの方へ
漢方理論をもとに女性の悩みに応えてきた一陽館薬局のかしたに陽子さんに、健康を保つ秘訣を聞く連載企画。今回は近年「腸活」という言葉とともに関心が高まっている、「腸内環境」についてのお話です。

腸内環境ちょっとした工夫で改善も
腸は免疫や代謝、精神面、美容にも影響
おなかの調子が好調な時は当たり前のように過ごしていても、一時的であっても便秘や下痢、腹痛、ガスがたまるなどの不具合が起きると、集中力低下、食欲不振や肌荒れ、気分のムラや睡眠の不安定さなど日々の生活にも影響が及ぶことがありますね。
かつて「腸」の役割は、食べ物の消化・吸収と不要物の排出に限られると考えられていましたが、近年では腸が免疫や代謝、精神面、美容にも影響を及ぼすことがわかってきました。そのため、「腸活」という言葉とともに腸内環境を整えて、全身の健康を支えるための取り組みに関心が高まっています。
日常生活において腸内環境を好ましい状態にするため、食事に気をつけたり必要な運動を取り入れる方もおられると思います。
理想的なバランスは善玉菌:悪玉菌:日和見菌=2:1:7
腸内には、約1000種類・100兆個以上ともいわれる腸内細菌が生息しており、「腸内フローラ(腸内細菌叢)」と呼ばれます。これらの細菌は大きく分けて、体に良い働きをする「善玉菌」、悪影響を及ぼす「悪玉菌」、どちらにもなり得る「日和見菌」に分類されます。
・善玉菌:腸内の有害物質を増やす悪玉菌の繁殖を抑える菌。
(例)ビフィズス菌、乳酸菌等
・悪玉菌:腸内の有害物質を増やす菌。
(例)ブドウ球菌、ウェルシュ菌
・日和見菌:腸内に善玉菌が多い場合は無害。悪玉菌が多いと悪玉菌と同じく有害物質を生み出す菌。
理想的なバランスは「善玉菌:悪玉菌:日和見菌=2:1:7」とされており、このバランスが保たれている状態が「腸内環境がよい」とされます。
腸内環境の悪化は病気にかかりやすい体に
腸には、「腸管免疫(ちょうかんめんえき)」という免疫システムが備わっており、体内の免疫細胞の6~7割が腸に集まっています。腸内環境が整っていれば免疫力が高まり、病原体の発見や情報伝達、病原体そのものへの攻撃などの役割により、風邪やアレルギーなどの病気にもかかりにくくなります。
一方で、腸内環境が悪化すると、免疫力が低下し、便秘や下痢、肌荒れ、感染症などさまざまな不調の原因にもなり、さらに過敏性腸症候群といった腸の病気をはじめ、花粉症や免疫系疾患などさまざまな病気の引き金になるかもしれません。
私たちが健康な毎日を送るために必要な腸管免疫は腸内環境が悪くなると機能が弱まってしまい、病原菌が体内で増殖を始めます。腸内環境の悪化は、病気にかかりやすい体になってしまうことにつながるといえます。
腸内環境が悪化するさまざまな原因
腸内フローラは一人ひとり異なり、善玉菌や悪玉菌のバランスは年齢や体調、生活習慣などによって刻々と変化しており、腸内環境が悪化する原因もさまざまです。
◎食生活
肉類や加工食品に偏った食生活では脂質や動物性タンパク質を好む悪玉菌が増え、相対的に善玉菌が減って腸内フローラが乱れやすくなります。
腸内細菌は食事で摂った食べ物をエサにしているため、暴飲暴食や過度なダイエットなども腸内環境を悪化させる要因となります。
◎加齢
年齢と共に腸内細菌の多様性も失われやすくなり、一般に60歳くらいになるとビフィズス菌などの善玉菌が減り始め、代わってウェルシュ菌などの悪玉菌が増えてくる傾向にあります。高齢になると便秘になる人が増えたり下痢を起こしやすくなったりする要因として腸内環境の変化が影響しています。
◎ストレス
過度なストレスで自律神経が乱れると腸の働きが低下し、悪玉菌が増えやすくなります。 腸の働きは自律神経によって支配されているため、腸内環境の悪化は"うつ"など心の病気を発症しやすいとされています。
◎薬の影響
抗生物質や服用期間などにより、腸内フローラのバランスが乱れることもあります。
便やおならで腸内環境の把握を
腸内環境を把握するには、便の状態を観察することが大切です。理想的な便は、「バナナ状」「黄色に近い茶色」「強くないにおい」です。硬くコロコロした便や、においの強い便、おならの回数が多い場合は悪玉菌が増えているサインかもしれません。特に赤や白い色の便が続く場合は、早めに医療機関の受診を検討しましょう。
腸内細菌のバランスがよい時、小腸では食べたものから栄養素や水分をしっかり吸収し、残りカスが大腸へと送られ、やがて便となり排出されますが、悪玉菌が優勢な時は、悪玉菌の出す毒性物質により大腸の蠕動(ぜんどう)運動を鈍らせてしまい便が滞り「便秘」となります。
また、悪玉菌が作り出す大量の有害物質を早く排出しようとする場合は便秘になるとは限らず、蠕動運動が活発になり過ぎて下痢になってしまうこともあります。
このような状態が続くと、腸内ではさらに悪玉菌が活発に働き、アンモニアやアミンなどの腐敗物や有毒ガスが発生します。これは臭いおならや便の原因となるだけでなく、腸の粘膜の毛細血管を通して全身にまわり、やがて皮膚から皮脂や汗にまぎれて排出されるため、肌荒れの原因にもなっていきます。
腸内環境を整えるために善玉菌を多く保つ
腸内環境を整えるためには、まず腸内での善玉菌の割合を多く保つことが基本です。
腸の状態がよくなると悪玉菌はすみづらくなり、反対に善玉菌は快適に働けるようになります。善玉菌を増やして、腸内環境を改善していきましょう。
腸内環境の改善のためのポイント
◎食事によるアプローチ
・食物繊維の多い食品……善玉菌のエサとなります
(例)海藻、豆類、キノコ類、ごぼう、押し麦など
・発酵食品……善玉菌そのものを補えます
(例)ヨーグルト、納豆、味噌、チーズ、キムチなど
・バランスの取れた食事……腸内環境を悪化させる要因を減らします
(例)砂糖・塩分・動物性脂肪の過剰摂取など
・規則正しい食事……腸の動きを促進し、排便のリズムを整えます
(例)朝食をしっかり摂るなど
◎運動・生活習慣によるアプローチ
・ウォーキング……腸腰筋を鍛えましょう
(例)1日8000~9000歩程度を目安に
・お腹のマッサージ……腸の動きを助けます
(例)手のひらでやさしく時計回りにお腹をマッサージ
・椅子に座ってできる足踏み運動……運動が難しい方でも腸への刺激が可能です
・十分な睡眠やストレス管理……腸内細菌のバランスを整える重要な要素です
◎漢方での腸活アプローチ
漢方では、腸内環境の乱れも「気・血・水」の巡りの偏りとしてとらえます。たとえば、ストレスや冷えによって「気」の巡りが滞れば腸の動きが鈍くなり、便秘につながります。便秘が続くと「瘀血(おけつ)」=血の滞りを生み、肌荒れや頭痛といった症状が現れることもあります。
便秘気味の方には、通便作用のある漢方薬を利用したり、冷えが原因なら温めて腸を動かすように働きかけます。下痢しやすい体質の方には、腸を温めて水分を調整する処方や、ストレス性の腸の不調には気の巡りを整えるように働きかけます。
☆ ☆ ☆
健康な毎日を支える腸内環境はバランスのよい食事や規則正しい生活など、ちょっとした工夫で整ってくると思います。少しずつできることから始めてみましょう。
※このページの内容は2025年4月18日現在のものです。