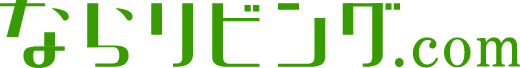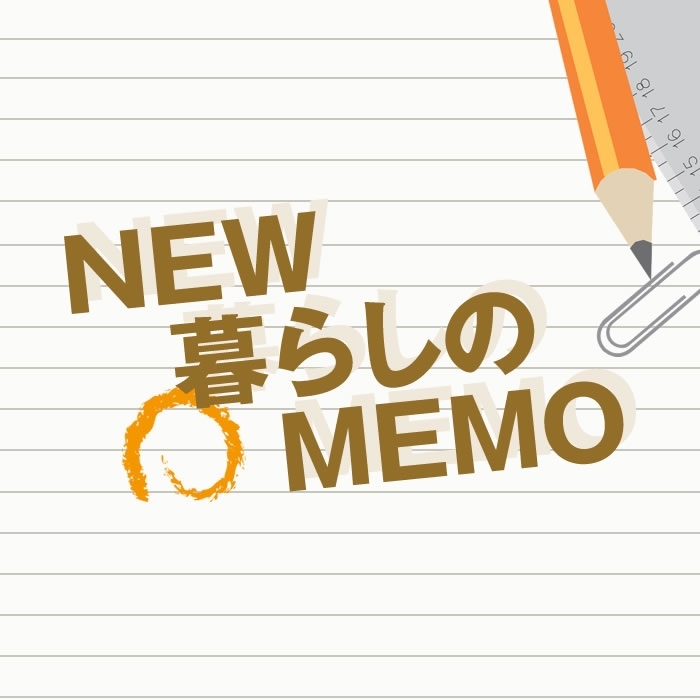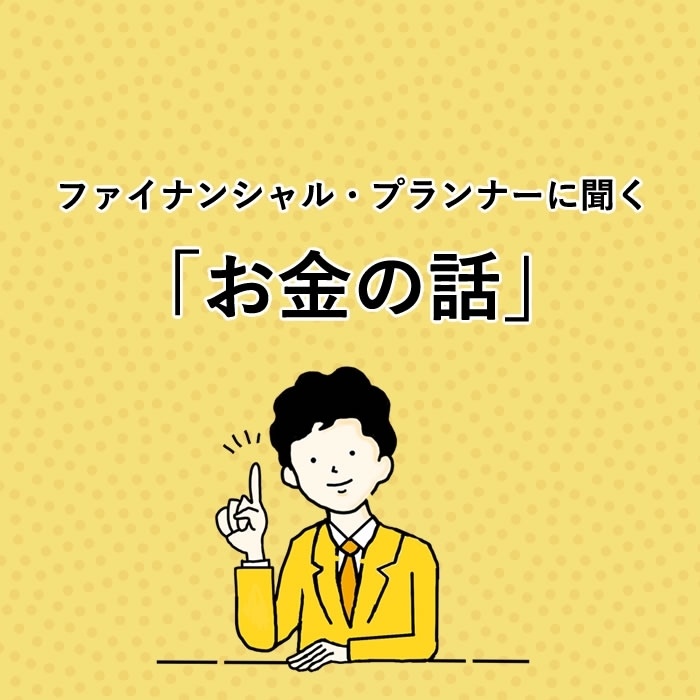漢方養生で日々健康~体質を知るともっと元気になれる~vol.31「痔」でお悩みの方へ
漢方理論をもとに女性の悩みに応えてきた一陽館薬局のかしたに陽子さんに、健康を保つ秘訣を聞く連載企画。今回は一人で悩んでいる人も多いと思われる、「痔」の悩みを持つ方に読んでいただきたいお話です。

成人の3人に1人は悩んでいる
どうしても恥ずかしさなどから相談しづらい症状のひとつかもしれません。症状が軽い段階では病院へ行くのも気がすすまず、積極的に治療するよりできれば生活養生で改善したいという声も聞かれます。
もしかしたら誰にも相談できずに一人で悩んでいる方も多いのではないでしょうか?
排便時の出血や肛門部に激しい痛みを起こす「痔疾(じしつ)」は、成人の3人に1人は悩んでいると言われるほど身近な病気ともいえます。特に女性では妊娠出産を機に発症したり悪化したりしやすく、その後慢性化してしまうケースも珍しくありません。
痔の種類と症状
痔核(いぼ痔)
「いぼ痔」には、肛門の内側にできる内痔核と外側にできる外痔核があります。便秘や妊娠・出産、長時間座りっぱなしの生活などが要因となって、肛門周りの静脈がうっ血してしまうことで起こります。肛門の内側や外側にできたいぼにより痛みや出血することもあります。
裂肛(切れ痔)
便秘などで便が硬くなって出にくかったり、逆に下痢などで便が勢いよく出てしまうなどにより、排便時に肛門の出口付近を傷つけたり切れてしまったりするものです。痛みや出血が起きることもあります。
痔瘻(あな痔)
細菌が肛門の組織に入り込んで化膿し、皮膚に向かって膿のトンネルができて激しい痛みと腫れ、発熱する場合もあります。手術が必要になることもあり、早めの受診が必要です。
痔になる主な原因は
痔になる主な原因としては、便秘や下痢など直接肛門に刺激となるもののほか、排便時に強くいきんで圧がかかったり、座りっぱなしによるうっ血などがあげられます。たとえば、便秘で便が硬くなると排便時にいきみが強くなり、肛門出口に圧力がかかって切れ痔になったり、血管の集まった部分がうっ血していぼ痔になったりする場合があります。
また、スパイスのきいた辛い食べ物や飲酒など刺激になる食物や、デスクワーク中心の長時間座りっぱなしの姿勢など、おしりに負担がかかりやすい食事や生活習慣も痔の発症や症状の悪化に影響するといわれます。
痔の治療法
西洋医学(病院)での治療法としては、主に薬物療法と手術療法の2つがあります。
薬物療法は比較的症状が軽い段階が対象で、便通を安定させるために整腸剤や便を軟らかくして排便時の負担を軽減するための薬のほか、痛み止めや出血・腫れを抑える座薬や注入軟膏などが使用されます。
痔の症状が悪化して、薬による治療だけでは改善が難しくなると手術の対象となります。
痔は日常生活の影響が大きく、要因となる生活習慣を改善することが大切です。いったん治ったとしても、好ましくない習慣を続けていると再発にもつながりますから、おしりに負担をかけない生活習慣を心がけましょう。痔を引き起こす直接的な原因である便秘や下痢といった、便通の異常を改善することが改善と予防につながります。
生活習慣の改善を
◎便質を整えるために食物繊維や水分を摂りましょう
便質を整える作用がある食物繊維が不足すると腸の動きが鈍化して便が硬くなってしまいます。野菜や果物類、海藻類など食物繊維の豊富な食材を活用したいものです。
また適度な運動は腸の動きも活発になり、スムーズな排便につながります。全身の血液循環もよくなり肛門部の血行不良によるうっ血も改善することができます。
◎下痢を防ぐ工夫をしましょう
食べ過ぎ飲み過ぎといった暴飲暴食に注意し、消化のよい食事で消化不良が起こらないよう心がけましょう。 お腹が冷えやすい人は季節や温度差に合わせて寒い時期は衣類で調節したり夏場は冷房による冷えにも対策しましょう。
◎便通を安定させましょう
無理なダイエットで食事の量を極端に減らしたり偏食などで便の材料が不足すると便の量も十分でなく排便も不規則になります。また規則正しいリズムを整えるために便意があったら我慢せずトイレに行くことや長時間いきまないなども大切です。
◎知っておきたいNG食材
香辛料などの刺激物は、辛みの成分が消化されずに便の中に残り、肛門の粘膜を直接刺激することがあります。アルコール類は末梢血管を拡張することでうっ血を招き悪化の要因となります。
漢方治療では体質改善を
症状が出てからおこなう「対症療法」では、痛みがあれば痛み止め、出血すれば止血剤、いぼが大きくなれば切除する、といった症状を取り除く治療が中心となりますが、日常生活の改善と合わせて痔を起こしやすい体質から改善するという意味では漢方治療も効果的です。
漢方では「うっ血」による症状は「瘀血(おけつ)」=血の巡りの滞りが原因と考え、血行を良くしたり温めたりする処方を用います。また「痛み」の症状には炎症を鎮める処方を用い、疲れやストレスで悪化する場合は「気」を補ったり巡りをスムーズにする処方を用います。
具体的には、最もポピュラーな乙字湯(おつじとう)のほか、便秘の程度に応じて桃核承気湯(とうかくじょうきとう)や大黄牡丹皮湯(だいおうぼたんぴとう)、生理周期やホルモンバランスが関係する場合は桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)や加味逍遥散(かみしょうようさん)、体質的にお腹が弱いタイプには状況に応じ補中益気湯(ほちゅうえっきとう)や建中湯(けんちゅうとう)などから適切なものを選んでいきます。
「痔」は厄介なイメージを持たれがちですが、実際のところは、無理し過ぎて疲れがたまっていたり、ストレスをため込んでいたり、食生活や生活習慣が乱れていたりなど、ご自身の調子を示すサインとも受け取れると思います。
"あッ、またか?!"と思われた時は、ゆったりお風呂につかって血行促進しながら気分的にもリラックスしてみるのもよいのではないでしょうか。
※このページの内容は2024年7月19日現在のものです。