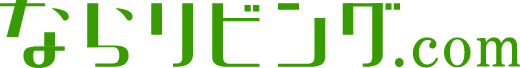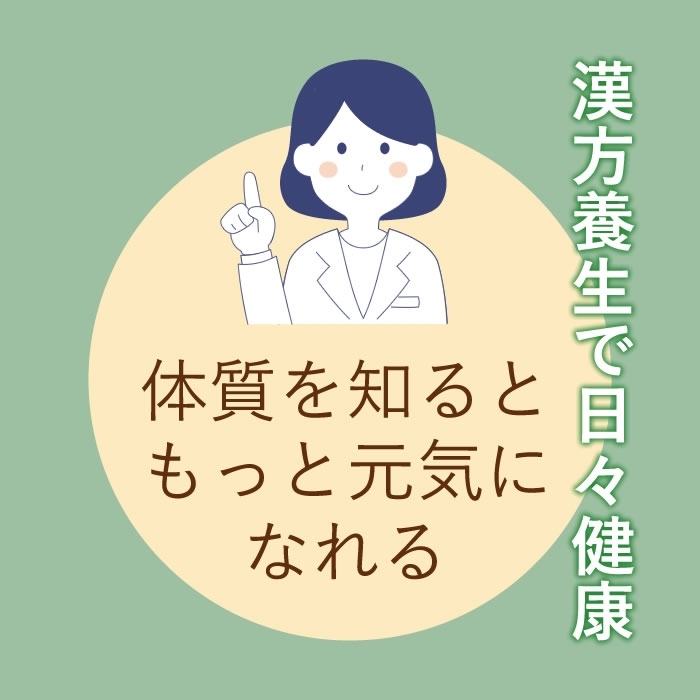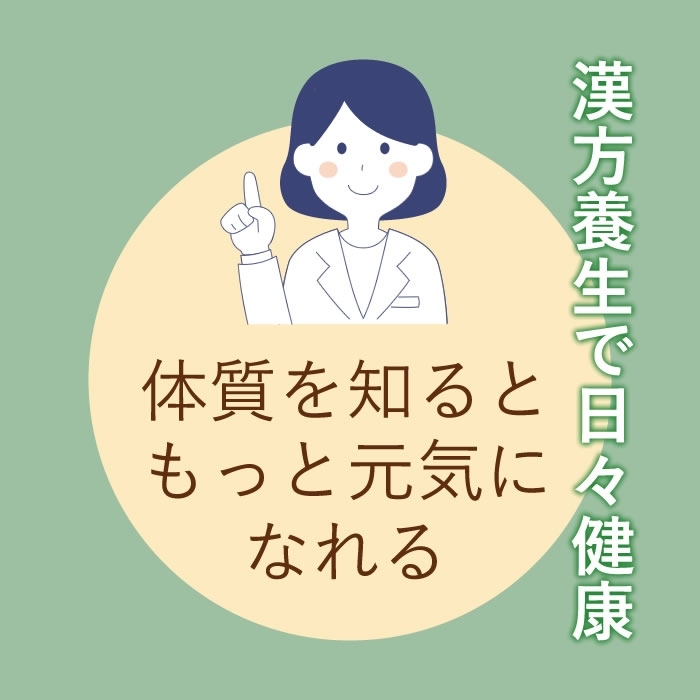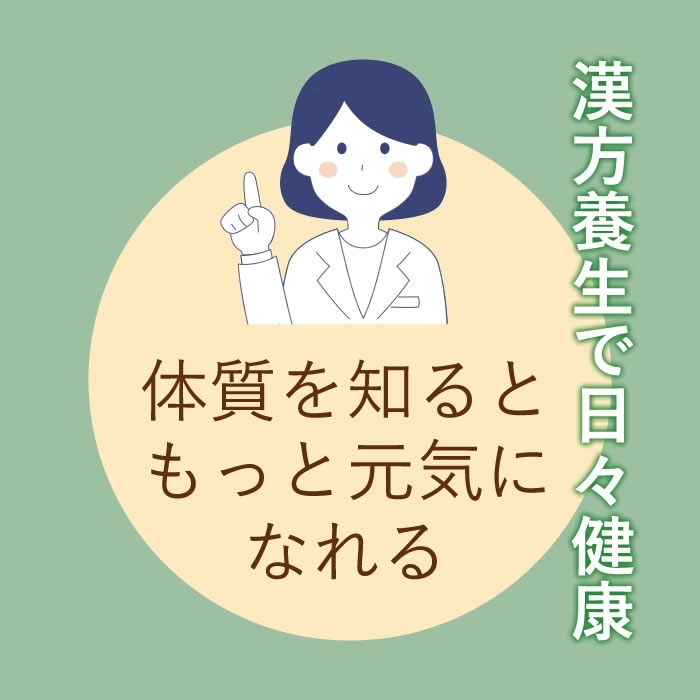漢方養生で日々健康~体質を知るともっと元気になれる~vol.37「足の“つり”」にお悩みの方へ
漢方理論をもとに女性の悩みに応えてきた一陽館薬局のかしたに陽子さんに、健康を保つ秘訣を聞く連載企画。今回は突然訪れ、経験した人も多いと思われる「足の〝つり〟」についてのお話です。

筋肉の収縮と弛緩のバランスが崩れて起こる
ふとしたタイミングで不意に訪れる激痛、頻繁に足がつると辛いものです。
足のどの辺りが、どんな時につってしまうのかはライフスタイルによって人それぞれですが、若い頃と比べ「つる場所」や「つり方」が変わってきたという方や、季節により発症頻度が変わるという方もおられるかもしれません。
いわゆる「足がつる」現象は、筋肉がけいれんして痛みを伴う状態をいいます。
足がつる原因である「筋肉のけいれん」は、筋肉が収縮し続けて弛緩できない状態に陥るために起こります。通常時は、筋肉の動きは神経からの信号によって制御されており、収縮と弛緩のバランスがとれていますが、筋肉内の神経や電解質バランスが崩れるなど何らかの異常があると、この制御がうまくいかなくなります。
足がつる主な原因
1. 水分不足
汗をかき過ぎたときや水分補給が不足したときには、筋肉の働きを調整するのに必要な電解質(ナトリウム、カリウム、マグネシウム、カルシウム)が不足することで、筋肉の収縮と弛緩のバランスが崩れます。
2. 電解質バランスの乱れ
食事の偏りや脱水症状などにより、電解質に過不足が生じると筋肉の興奮性が高まり、けいれんを引き起こすことがあります。
3. 筋肉の疲労
過度の運動や長時間の歩行や立ちっぱなしの仕事などで筋肉が疲労し、酸素や栄養素が不足すると筋肉が緊張し、けいれんを起こしやすくなります。
4. 血流不足
冷え性、動脈硬化、正座など圧迫された姿勢などで筋肉への血流が減少すると、酸素の供給が不足し、けいれんが起こることがあります。
5. 神経の異常
脊髄や神経の障害、椎間板ヘルニアなどの疾患では、筋肉をコントロールする神経への刺激に異常が生じ、筋肉が過剰に収縮することがあります。
6. 低血糖
食事をとらないなど空腹の状態や糖尿病治療薬の副作用などにより血糖値が低下すると、エネルギーが不足し筋肉の正常な働きが妨げられることがあります。
7. 寒冷環境
冷たい水で泳いだときや冬の屋外作業などでは筋肉が冷えて緊張しやすくなり、けいれんを引き起こすことがあります。
8. 特定の薬の副作用
利尿剤や降圧薬など、一部の薬が電解質バランスに影響を与える場合があります。
足がつる場所による違い
具体的な場所ごとに原因や背景には違いがあります。
1. ふくらはぎ(こむら返り)
「こむら」というのはふくらはぎの古い呼び名で、突然の痛みとともに、筋肉が硬くなります。
主な原因として、筋肉疲労、脱水や電解質の乱れ、冷え、運動不足など最も典型的なものです。
2. 足の裏
足指が内側に引き込まれるように感じ、強い痛みを伴います。
主な原因として、 足の疲労や偏平足、サイズが合わない靴や硬い靴底などによる過剰な負担、足底筋への負荷が偏りやすいなどがあげられます。
3. 足の指
特に親指や小指が内側や外側に引っ張られるようにしてつり、動かしづらくなります。
主な原因として、冷えて指先の血流が悪くなったり靴による圧迫、指先の運動不足や過剰運動、 糖尿病や循環器疾患による末梢神経障害などがあります。
4. 太もも(前側・後側)
脚全体が動かしにくくなり、かなり強い痛みを感じることがあります。
主な原因として、ランニングやサイクリング後などの筋肉疲労、水分不足と電解質異常、長時間座りっぱなし、または立ちっぱなしなどによる筋肉の硬直、腰椎から太ももの筋肉にかけての神経が圧迫されることなどによります。
5. すね
足首やつま先が強く引っ張られ、歩きづらくなることがあります。
主な原因として、運動不足や血流不足のほか、筋膜の柔軟性が低下し、筋肉のけいれんを起こします。
体からのサインととらえ適切な対応を
足のつりには、電解質バランスや血流、神経などが関係しており、頻繁に発症する場合は食事、水分補給、運動、疲労など生活習慣を見直すことも大切です。特定部位に起こりやすい場合は、姿勢や靴の選び方などにも注意してみると対策に気づくことができるかもしれません。
冬場は冷えが関係することも多く、防寒対策や適度な運動も効果的です。
足がつりやすい人の背景としては、妊娠中(ホルモンの影響や血液循環の変化)、高齢者(筋肉量や代謝の減少、血流の低下)、持病を持つ人(糖尿病、腎臓病、甲状腺疾患)などがあげられます。
予防策としては、十分な水分補給やバランスの良い食事、適度な運動やストレッチの習慣、体を冷やさない(特に足元を温かく保ち血行を促進する)、圧迫のない衣類や靴を選ぶ、足湯や温湿布などもおすすめです。
食品では、電解質バランスに配慮し、マグネシウム(ナッツ類、葉もの野菜)、カリウム(バナナ、芋類)、カルシウム(小魚)を含むものがおすすめです。
漢方薬では、足のつりには電解質バランスを整える作用がある「芍薬甘草湯」が知られていますが、冷え、ストレス、疲労、体力不足など個々人の体質的要因を整えることで「つりにくい体質」へ向かうことができますので、色々試しても治まらない場合はご相談ください。
足がつるのは、日常生活に密着したトラブルのひとつですが、体からのサインととらえ、適切な対応をとることで快適な毎日をお過ごしいただきたいと思います。
※このページの内容は2025年1月24日現在のものです。