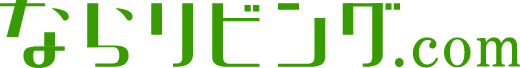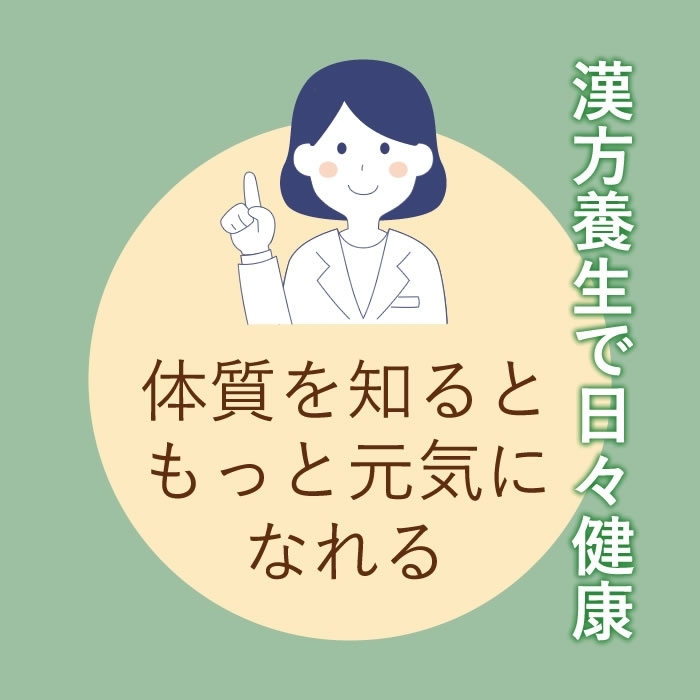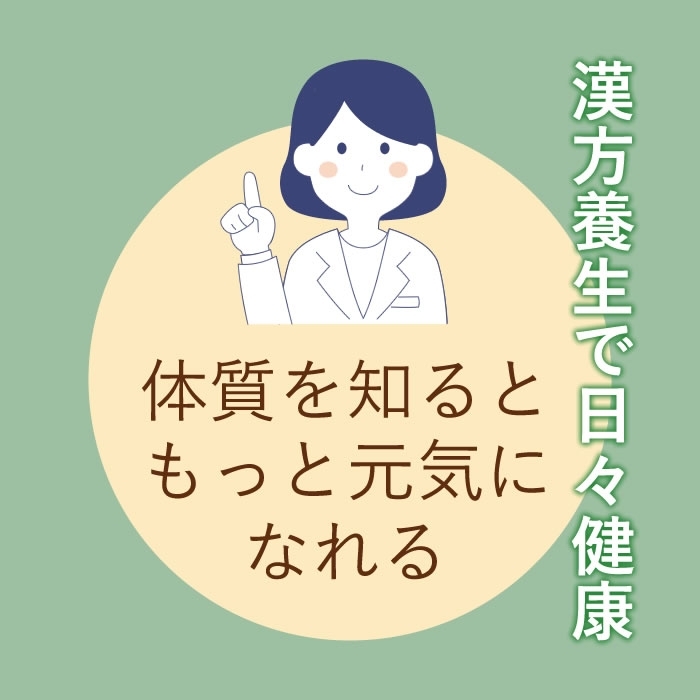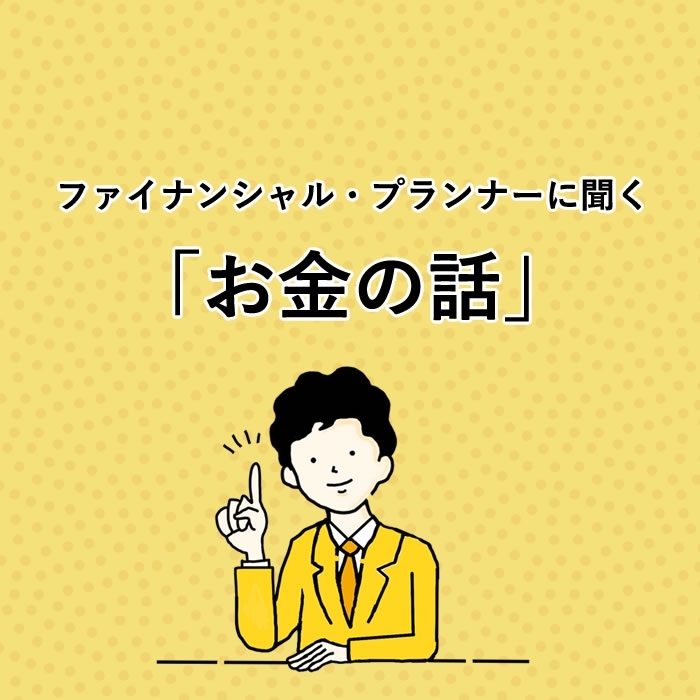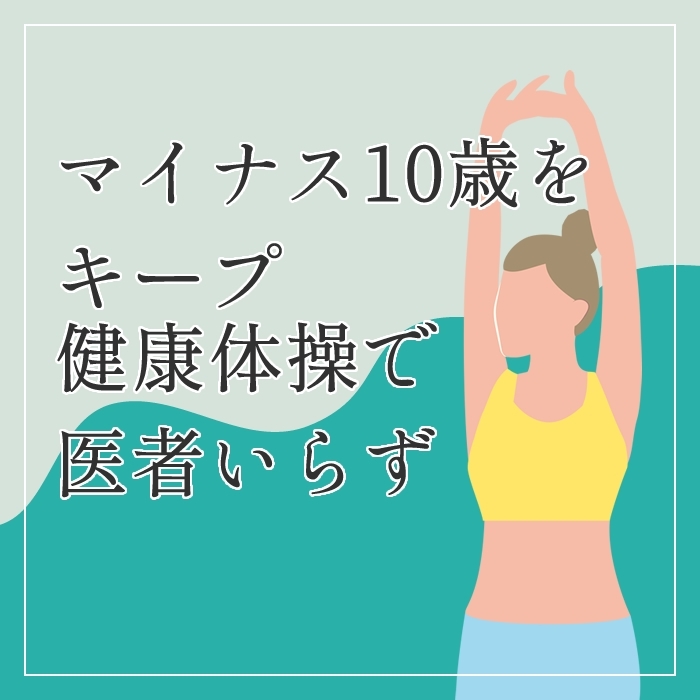漢方養生で日々健康~体質を知るともっと元気になれる~vol.41「目の不調」が気になる方へ
漢方理論をもとに女性の悩みに応えてきた一陽館薬局のかしたに陽子さんに、健康を保つ秘訣を聞く連載企画。今回は、何となく不調を感じている人も多く、誰にでも起こりうる「目の不調」についてのお話です。

目を使いすぎる時代、グレーゾーン不調も
最近、「目がしょぼしょぼする」「乾く」「まぶしい」「疲れる」といった不調を訴える人が、年齢を問わず増えていると感じます。眼科に行っても「異常なし」だとホッとする反面、なんとなくスッキリしないまま日々を過ごしている人も多いのではないでしょうか。
現代は"目を使いすぎる時代"と言われます。スマートフォンやパソコン、LED照明、オンライン会議など日常生活で酷使され続け、負担が大きくなっているにもかかわらず、十分に疲れを回復しきれないまま無理が重なり、働きそのものが弱っているのかもしれません。
目は私たちの感覚器官の中でも常に最前線で情報をキャッチし、外からの刺激を受けやすい状況にあり、しかも休ませづらい器官です。病気になる手前の「グレーゾーンの不調」が潜んでいる可能性も考えられるのです。
では、どのような人が、どのような "目の不調" を抱えやすいのでしょうか。日常の中のよくある症状と、そこから考えられる背景、そして最近増加傾向にある"病気"との関係について、世代別に見ていきましょう。
生活の質に影響しているのであれば立ち止まって考える必要も
「目がつらい」と感じるのは、具体的にはどのような症状が起きていますか。
たとえば、"乾く" "かすむ" "まぶしい" "しょぼしょぼする" といった一見すると「よくある疲れ目」のように思えても、それが毎日続いていたり、生活の質に影響しているようであれば、ちょっと立ち止まって考えてみる必要があるかもしれません。
というのも、現代は目の使い過ぎだけでなくストレスや睡眠不足、食生活の乱れなど環境要因も加わり、単なる"局所の問題"では済まなくなっていると考えられるためです。
10代後半から20代の若い世代「調節障害」や「スマホ老眼」
10代後半から20代の若い世代に増えているトラブルとして、スマホやタブレットの見すぎによる「調節障害」や「スマホ老眼」があります。スマホをずっと見る習慣、夜のベッドの中でも画面を見る生活が、目の調節機能を限界まで使わせてしまっているのです。これは、本来なら遠くと近くを見るたびに切り替わるピント調整の機能が、長時間の近業でうまく働かなくなってしまう状態です。視界がかすむ、目の奥が痛む、まぶしさに敏感になるなどの症状が出ることもあります。
こうした「目の緊張」は、ただ "目だけ" の問題ではなく、ピントを合わせる筋肉が緊張し続けることで、全身の自律神経にも負担がかかり、頭痛や吐き気、肩こりにつながる場合も見受けられます。
また、画面を長時間見ていると自然とまばたきの回数が減ってしまい、涙が蒸発しやすくなります。これが、若年層にも見られる「ドライアイ」の一因に。目の表面を保護する涙が少なくなることで、角膜に炎症が起きやすくなり、"なんとなく目がゴロゴロする" "目が開けにくい" といった違和感につながります。
対策としては、1時間に1回は画面から目を離し、遠くを見る「目のリセットタイム」をつくること。また、目を温めたり、目の体操で筋肉をゆるめたりする習慣も効果的です。
若いから大丈夫といっても「目は酷使すれば傷む」という認識をもつことが大切です。
30代から50代の働き盛り世代「慢性的な眼精疲労も」
30代から50代のいわゆる "働き盛り世代" では、パソコン作業やストレス過多による慢性的な眼精疲労が深刻化しているようです。医学的には、目のまばたきが減る→涙の蒸発量が増える→ドライアイになるというメカニズムがよく知られていますが、それだけではありません。目の奥の重だるさ、夕方になると見えにくくなる、イライラや不眠がセットで起きる、といった症状にお悩みであれば、それは「VDT症候群(Visual Display Terminal症候群)」といわれる、つまり画面を見続けることによってまばたきが減り、目の表面が乾燥するだけでなく、交感神経が優位になりすぎることで自律神経が乱れ、結果として目だけでなく体全体の不調を引き起こす状況かもしれません。
また、"まぶしさが苦手になった" "人混みで視界がつらい" と感じるという悩みも聞かれますが、これは視神経や脳の視覚中枢が光に過敏に反応している状態。眼球そのものよりも、むしろ脳の疲労が影響しているようなケースもあるのです。
この年代の目の不調は、「頑張りすぎ」と「ストレス過多」の結果として現れていることも多く、根本的には"緊張状態から抜ける時間"をどれだけ持てるかが大切なことです。
60代以降のシニア世代「加齢以外の要因による不調も」
60代以降のシニア世代では、「目が乾く」「見えにくい」「まぶしい」「黒いものが飛んで見える(飛蚊症)」といった症状が現れやすくなります。加齢に伴う涙の分泌低下や、角膜の保湿力の低下によるドライアイは、以前よりも増加しており、その背景には生活環境の変化(エアコン、スマホ、LED照明など)も関係しており加齢だけでは片づけられない不調も多くなっています。
特に注目されているのが「加齢黄斑変性」。これは網膜の中心部にある"黄斑"という部分がダメージを受ける病気で、視界の中心がゆがんだり、黒く見えなくなるといった症状が出てきます。黄斑は細かいものを見るための非常に重要な部分で、紫外線やブルーライト、脂質の酸化などが大きく関わっていることが要因ともいわれます。
一見すると加齢による変化にも思えますが、最近は年齢以外の要因も関わる"質の悪い涙"によるドライアイが注目されています。つまり生活習慣病(糖尿病・高血圧)との関連も深く、目は全身の血流の状態を映す"鏡"ともいえるのです。
こうした疾患の初期段階では、見え方の変化がとても微細なため、気づかないうちに進行してしまうこともありますので、視野がゆがむ、色の感じ方が違う、夜間の見え方が悪くなったと感じたら、早めに眼科での検査を受けることも大切です。
「病気ではないけれど不調」というのは言い換えると「治療の対象ではないけれど支障がある」という状況で、漢方で疲労を回復したり弱りを補うことも効果的です。漢方では「腎の精が目を養う」とされ、加齢とともに「腎」の機能が弱くなることで目の力も衰えると考えられています。目を潤し、栄養を補う「肝」の働きとともに体の内側からサポートする考えがあります。
目薬やサプリだけに頼らず身体と暮らしを見直すきっかけに
では、目の不調を抱える人は、日々の生活でどんなことを見直せばよいのでしょうか?
例えば、朝から晩までスマホを見続けているなら、1日の中に意識的に"目を休ませる時間"をつくる、外の景色を5分でも眺める、1時間に1回は画面を閉じて遠くをぼんやり見るなど、それだけでも、目のピントを調整する筋肉の負担を軽減することにつながります。
また、お風呂にゆっくり浸かる、寝る前に部屋の照明を暗くしてスマホを見ない時間を設けるなど、自律神経を整える時間を持つと、体の緊張も緩和され、目の疲れも自然と回復しやすくなります。
そして、薬に頼る前に、日々の食事から「目を育てる」意識を持つことも大切です。私たちの体をつくる食事で養生を心がけましょう。目に良いとされる栄養素は、ビタミンA・C・E、ルテイン、ゼアキサンチン、オメガ3脂肪酸などがあげられますが、サプリだけに頼るのではなく、まずは基本の食事で補う意識を持つと充実した健康的な食事につながるのではないでしょうか。にんじん・かぼちゃ・ほうれん草・アボカド・青魚などを積極的に取り入れていきたいものです。
「見えづらい」「疲れる」といった目の不調は、実は私たちの身体や生活の状態を映す鏡のようなもので、ただの「器官」ではなく、心と体のバランスの影響を最も敏感に受ける"センサー"の役割を担っているといえます。
今の時代、誰にでも目の不調は起こりうる環境にありますが、「異常がないから大丈夫」と見過ごさず、「いつもと違うな」と感じたら、目薬やサプリだけに頼らず、身体と暮らしを見直すきっかけとして目を向けてみていただくことが健康維持にもつながることでしょう。
※このページの内容は2025年5月16日現在のものです。